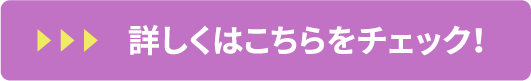2024年11月発売号で「2024ヒット商品ベスト30&2025ヒット予測ベスト30」を発表した日経トレンディと、電通の消費者研究プロジェクト「DENTSU DESIRE DESIGN」(以下DDD)が登壇した年末恒例のウェビナー「欲望(Desire)視点で紐解く2024年消費分析・2025欲望トレンド予測」。
このウェビナーでは、日経トレンディが毎年発表しているヒット商品ランキングの結果と、欲望視点で消費や流行を紐解くDDDの分析を振り返りながら、2025年の消費の流れや、流行・欲望トレンドを、日経トレンディとDDDそれぞれの視点で語りました。
本ブログでは、ウェビナーのエッセンスを再構成して、当日の模様を振り返ります。
INDEX
日経トレンディ「2024ヒット商品ベスト30」を紐解く
PROFILE
第1部では、日経トレンディの佐藤央明氏から、ヒット商品の傾向から見た消費のトレンドについて解説していただきました。そのダイジェストをお伝えします。
「日経トレンディ2024ヒット商品ベスト30」の対象は、2023年10月から24年9月の間に発売・発表された商品・サービス。「売れ行き」「新規性」「影響力」の3つの視点から、総合的な判定を行って、決定しています。
●「2024年ヒット商品ベスト30」のランキング選考基準
2023年10月から24年9月の間に発表・発売された商品・サービスを対象に、ヒットの度合いを評価した。具体的には下記の3項目に従って総合的に判定を行っている。期間前に発表・発売された商品でも、期間内に著しくヒットしたものは対象とした。昨年既にヒットしていた商品は、原則として対象外としている。「2025年のヒット予測」についても、同様の基準でランキングを行った。

2024年のヒット商品Best30のご紹介
こちらが2024年のヒット商品ランキングの上位30になります。 例年は、商品・サービス、施設やゲーム、エンタメ、外食など様々なジャンルの中で偏りがあることが多いのですが、今年はそれらがバランスよく入ったなというのが、選んでみての実感です。

日経トレンディでは、その年の「ヒット商品ランキング」だけでなく、同時に、翌年の「ヒット予測」も発表しています。ヒット予測は雑誌ならではのエンタメ色も重視し、「流行る商品」だけではなく、「面白い、夢のある商品」もランキングに加える傾向があります。
そんな中で、昨年の「ヒット商品予測」と、今年の「ヒット商品ランキング」を比較してみると、的中の精度が高かったように思います。例えば、昨年の予測では2位にアサヒビールの「未来のレモンサワー」を挙げましたが、一年前はほとんど知られていませんでした。今年のヒット商品では11位にランキングされています。
また、昨年の予測で「痛いコスメ」として7位でご紹介した「リードルショット」が、今年のヒット商品では4位にランキングされました。来年の流行にも期待しながら、楽しんでいただきたいと思っています。

2024年ヒット商品の3つの特徴
私が考える2024年のヒット商品の3つの特徴は、1番目が「ポジティブ生活防衛」。2番目が「推し活&レトロ」。3番目が「本気の定番ブランド」。3つのキーワードを紐解きながら、今年のヒット商品の特徴を見ていきたいと思います。
① ポジティブ生活防衛
何といっても「お得」や「生活防衛」にまつわる商品やサービスが多かったのが、2024年のヒット商品の特徴ですね。先ほどご紹介した表の1位と3位の「新NISA」「Vポイント」に加えて、国内倉庫からの直送システムで短納期&コスト削減を実現し、数千万人が利用するECサイトに成長した「Temu(テム)」。スポットワークに対するハードルを取り除くことで800万人の登録を獲得した「メルカリ ハロ」。最安1600円のうな重を実現し、わずか1年間で244店オープンの快進撃となった「鰻の成瀬」などが、このカテゴリーの代表です。
2024年は日経平均株価が史上最高値を更新するなど、景気が良くなったと言われていますが、我々消費者としては物価高などもあってなかなかその実感が持てない、というところかと思います。そんな中で、いかにして自らの資産を増やしていくのか。「新NISA」や「Vポイント」に代表されるような、積極的に投資やポイ活などを楽しむ「ポジティブな生活防衛」が今年の特徴と言えると思います。
② 推し活&レトロ
2024年は、「名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)」「劇場版ハイキュー‼ゴミ捨て場の決戦」などアニメ発の映画が大きなヒットになりました。こういった傾向は2018年頃を境に顕著になっているのですが、背景にはZ世代の台頭がある、と分析しています。
商品の機能が一巡して、モノやサービスを選ぶ際に、機能ではなく情緒で選ぶ時代。その情緒とは何かというと、レトロであれば、歴史とかストーリー。推し活の場合も、当然その人にまつわる物語があったりするわけで、そこが、Z世代だけではなく、多くの人々を引き付ける要因になっているのではないかと解釈しています。
③ 本気の定番ブランド
今年は食品・飲料を中心に、大手の新ブランドからヒットが生まれた年でもありました。キリンビール「晴れ風」や、アサヒビール「未来のレモンサワー」がその象徴ですね。数年前までは「一番搾り 糖質ゼロ」やスーパードライの「生ジョッキ缶」など、既存ブランドからのエクステンションが主流だったように思いますが、今年は本気の新ブランドがしっかりヒットした、という印象です。20位のハウス食品「クロスブレンドカレー」もそうですね。新ブランドの投入もラインエクステンションもマーケティングとしてはもちろんどちらも正解だと思いますが、既存ブランドを中心としたマーケティングから少し変化してきているのではないか、と言うのが実感です。
※なお第1部では、さらに過去10年にわたる商品・サービスのジャンルごとのヒット商品のトレンドについてご紹介いただきました。
● 日経トレンディ「2024ヒット商品ベスト30」の詳しい内容はこちらから
2024年ヒット商品ベスト30:日経クロストレンド
●日経トレンディ「2025年ヒット予測ベスト30」の詳しい内容はこちらから
2025年ヒット予測ベスト30:日経クロストレンド
DENTSU DESIRE DESIGN 2024-25年の欲望トレンドを語る
PROFILE
第2部では、ヒット商品の背景にある、日本人の「欲望」の現在地について、DDD(※)のメンバーの佐藤尚史と千葉貴志が、今年のヒット事象から導き出した知見について語りました。
※DENTSU DESIRE DESIGN(DDD)とは
消費者の「欲望(Desire)」に着目した電通のソリューション部門横断の研究開発組織。
ニーズの手前にある「欲望(Desire)」を可視化・構造化し、定量的・定性的に把握することで、消費者の「心が動く消費」の実現を支援しています。 また、消費における欲望をあぶり出す「心が動く消費調査」を定期的に実施しています。
DDDに関する情報はこちらもご覧ください。
● “欲望”基点のマーケティング支援サービス「DENTSU DESIRE DESIGN(デンツウ・デザイア・デザイン)」
● 欲望に応える商品開発のプロセスとは?『心が動く新商品開発プログラム』
● 欲望視点で紐解く2023年のヒット商品とは?日経トレンディとDDDが解説!
● 【事例】「心が動く」に着目し、100年企業の新商品開発にブレークスルーを!
DDDでは、独自の研究と分析に基づいた2024年度の「6つの欲望トレンド」を発表しています。

その中からここでは、「ポジティブ・ブースト」「シン『竹』」 についてご紹介します。
※「トレンドデトックス」「韓国というPOPフィルター」「ヤバめの代償求む」につきましては、
ウェブ電通報で解説記事を掲載しております。こちらも併せてご覧くださいませ。
2025年の欲望トレンド、「トレンドデトックス」。──日経トレンディ×電通の徹底分析!
2025年の欲望トレンド、「韓国というPOPフィルター」「ヤバめの代償求む」──日経トレンディ×電通の徹底分析!
欲望トレンド「ポジティブ・ブースト」

2024年の現在、私たちの周囲に目を向けると、戦争が続き政治的な混乱も各所で見られるなど、世界は不安定な状況にあります。日本国内でも先行きが不透明で経済的負担が増加している一方で、個人のレベルでは、日々接するスマホ画面を中心に、半ば強制的に「もっと成長、成功を/もっと外見も美しく」といったプレッシャーを感じるような情報が浴びせられる状況になっています。
そんなネガティブな環境に身を置きながらも、「心の底からポジティブでいたい」「優しい環境で過ごしたい」、そして「自分自身を肯定したい」という強い願望が、より一層ポジティブなものを求める気持ちへと繋がった。2024年はそんな一年だったのではないでしょうか。この「ポジティブ・ブースト」を要素分解して、より深く解説していきたいと思います。

● A「“前向き”神のご利益」

「“前向き神”のご利益」とは、大谷翔平選手のようなスーパースターやポジティブなイメージを持つ商品に関連するアイテムを求める消費者の心理です。大谷選手関連グッズの売れ行きがその代表例で、彼の活躍に連動して、彼が着用する私物や家族が持つブランド品までが飛ぶように売れました。これは、消費者が成功した大谷選手の要素を少しでも取り込みたいという願望の表れです。また、「未来のレモンサワー」や「+tmr(プラストゥモロー)」のような明るい未来を感じさせる商品も、消費者のポジティブな感情に訴えかけ、人気を集めました。
● B「優しさフィルターバブル」

近年、広告は過激な表現や強い圧力をかけるものが主流でしたが、消費者の間では、穏やかで優しい雰囲気を求める声が高まっています。キリンビールの「晴れ風」は、その代表的な例で、優しい色合いやネーミング、そして社会貢献活動を通じて、消費者の心に寄り添うことで大きな支持を得ています。
「休みながら美しく“休息美容”」というコンセプトのもとに、音・泡・感触・香りで五感に働きかけ、ヘアケアタイムを「自分を大切にする時間」に変える花王の「メルト」や、同じ花王の入浴剤「バブ あふれるのはきっと、お湯だけじゃない」も、同様に消費者の心の癒しを追求した商品となっています。これらの事例は、消費者の価値観が変化し、より穏やかで優しいものを求めていることを示唆していると言えるのではないでしょうか。
● C「“界隈”による心理的安全生活」

近年、価値観が多様化し、個人のライフスタイルがますます細分化しています。そんな中、「〇〇界隈」という言葉が、特定の趣味やライフスタイルを持つ人々のゆるやかなコミュニティを指す言葉として定着しました。「お風呂キャンセル界隈」(お風呂に入りたくない人たち)や「伊能忠敬界隈」(散歩が大好きな人たち)など、一見するとニッチなコミュニティも、SNSを通じて繋がり、共感が広がっています。これらのコミュニティ内では、商品情報が活発に交換され、新たな消費を生み出す現象が見られます。「界隈」という場を通じて、消費者自身が情報を交換し、ヒット商品を生み出すという新しいマーケティング戦略に、企業は注目する必要があるということです。
● D「自己肯定オルタナティブ」

「ポジティブ・ブースト」の4つめは、「自己肯定オルタナティブ」です。その中をさらに3つに細分化すると、自分の劣等感を吹き飛ばしてくれるようなコンテンツが人気となった「自己肯定感の無条件爆上げ」。次に、特定の価値軸への過集中に対抗する新しい評価軸の提案をする「自己肯定新機軸の提案」。それでもダメなら中身は整わなくても、外から見た時の自己肯定感を武装しようという「自己肯定の武装化」です。
では、一つずつ解像度を上げてご紹介していきたい、と思います。
<D-1「自己肯定感の無条件爆上げ」>

近年、SNSなどを通じて自分と他者を比較することで、自己肯定感を下げてしまう人が増えています。そんな中、音楽業界を中心に「自己肯定感の無条件爆上げ」をテーマにした楽曲やコンテンツが流行しています。例えば、アイドルグループ「FRUITS ZIPPER」の『NEW KAWAII』は、自分を追い込む世間の評価軸から解放され、ありのままの自分を肯定するメッセージを歌っており、多くの人々に共感を得ています。他にもヒップホップなどの音楽ジャンルやアニメーション、さらには出版の世界まで、様々な分野で自己肯定感をテーマにしたコンテンツがヒットしていて、現代社会においていかに「自己肯定感」が求められているのか、を示しているものと言えそうです。
<D-2「自己肯定新機軸の提案」>

従来の評価軸から脱却し、多様な価値観に基づいた自己評価が求められるようになっています。「スマドリ(スマートドリンキング)」のように、お酒を飲めない人も楽しめるような新しい飲み方の提案や、「メンズ日傘」のように、性別に捉われない商品もヒットしています。
「MBTI診断」のように、SNSで自分のパーソナリティを判定することも一般的になり、人々は自分にとって最適なライフスタイルや価値観を模索するようになっていると言えるでしょう。
<D-3「自己肯定の武装」>

現代人は、周囲からの視線や自分自身への厳しい評価から、なかなか自己肯定感を持てずにいます。そこで、「多幸感メイク」のように、見た目で幸せを演出したり、「GRL(グレイル)」のように、手軽に手に入る高品質なアイテムで自信を高めたりするなど、自己肯定感を高めるための様々な手段を講じています。これらの行動は、単に外見を変えるだけでなく、心の状態にも影響を与え、自己肯定感を高めることで、よりポジティブな生活を送りたいという人間の深層心理を表しているのではないかと思います。
● 「ポジティブ・ブースト」まとめ
SNSの普及によって、特定の価値観が拡散されやすく、多様な価値観が認められにくい社会となっています。この現象は、エコーチェンバーと呼ばれるように、自分と似た意見を持つ人々との間で意見が固定化されることで起こります。このような状況下では、多数派の価値観に合致しない人々は、強い疎外感やフラストレーションを感じてしまいます。そこで、多様な価値観を持つ人々を受け入れ、肯定的なメッセージを発信するような製品やサービスが求められるようになっています。これらの製品やサービスは、人々の心を癒し、自己肯定感を高めることで、より良い社会の実現に貢献する可能性を秘めています。

欲望トレンド「シン『竹』」

日本を含め、文化や消費が成熟しきった国では、松・竹・梅のうち、高価格帯の「松」か低価格帯の「梅」への買い分けが進む、いわゆる「メリハリ消費」が常態化していると言われています。特に日本では、コストプッシュ型のインフレの影響で、中価格帯の「竹」だったものが、実質的にも体感的にも高価格帯にシフトしてしまった、という状況があります。その結果、日本人の消費感覚から中価格帯が抜け落ちてしまったような気がしますが、その抜け落ちた中価格帯に、必ずしも価格の中庸ということだけに限定されない、新しい個性や切り口を持った「シン竹」が次々と誕生したのが2024年だったように思います。

「竹」である以上、中価格帯であることが大前提ですが、「シン竹」は単なる中庸ではなく、そのジャンルにおける従来の評価軸とは異なる新しい切り口を持ち込んで、新しいポジションを形成しているのが特徴です。その代表例が「鰻の成瀬」ですね。鰻の成瀬の場合、1600円という手頃な価格が魅力であることはもちろんですが、加えて、店内はカフェのような雰囲気で、鰻屋さんとしての新しい軸を打ち出していると思います。
他にも、JAL、ANAの「プレミアムエコノミー」は従来のエコノミークラスでは味わえない新しい体験を提供する、体験の「シン竹」だと思いますし、「コストコ再販店」の場合は、言ってみれば「アクセスしやすいコストコ」ということになるのではないかと思います。ハウス食品の「クロスブレンドカレー」は味の「シン竹」。従来のカレーは、「大人の辛口」「子どもの甘口」といった感じでしたが、このカレーは、スパイスをうまく工夫することで、大人も子どもも満足できる、味の新機軸を打ち出しています。
●「シン竹」まとめ
大きな枠組みで言うと、高価格帯は「ステータス」、低価格は「アフォーダビリティ」(手の届きやすさ)とか「コスパ」というような枠組みでとらえられると思います。それに対して中価格帯には、多くの人が「もっと自由度があるんじゃないか」「もっと遊び心が活かせるんじゃないか」と、気づき始めているのではないでしょうか。そのような枠組みの捉え方の変化、大胆なリフレーミングによって、今再び中価格帯、即ち「シン竹」に新たな価値が生まれる可能性が見えてきたのではないかと思います。これはかなり大きなマーケティングのヒントなりそうです。

パネルディスカッション:2025年の消費と欲望
最後に、「2025年の消費と欲望」というテーマで、日経トレンディの佐藤央明氏と、DDDの佐藤尚史のディスカッションが行われました。そのエッセンスをお伝えします。
2024年の消費トレンド /シニア層のデジタル化と新たな消費トレンド
近年、シニア層のデジタル化が急速に進み、消費の中心としての役割がますます大きくなっています。スマホの利用率が90%を超えるなど、デジタルデバイスへの親和性が高まり、オンラインショッピングやSNSの利用も活発です。フィットネスジムの利用や美容への関心も高く、若年層との共通点も多くなっています。
しかし、シニア層ならではの特性も存在します。例えば、デジタルデバイスの導入初期で、「オンボーディング」(順応を促進する取り組み)の重要性が指摘されており、丁寧なチュートリアル(個別指導)やサポートが求められます。また、シニア層特有の悩みや関心に基づいた商品やサービスが求められています。(日経トレンディ佐藤央明氏)
シニア層のデジタル化は、彼ら自身の生活を豊かにするだけでなく、新たな消費トレンドを生み出す可能性を秘めています。企業は、シニア層のニーズを的確に捉え、彼らに合わせた商品やサービスを提供することで、大きなビジネスチャンスが得られるのではないでしょうか。(DDD 佐藤尚史)
2025年のマーケティングへのヒント
● 日経トレンディ佐藤央明氏「タイパ」の逆張りの「ヤバめの代償」
今回の「ポジティブな生活防衛」も、インフレ下で消費者の意識が変化し、今後も注目されるキーワードになると考えています。一方で、効率重視の「タイパ」一辺倒から、あえて時間をかけて楽しむニップンの「もちっとおいしいスパゲッティ」のような商品が人気を集めるなど、多様な価値観が求められる時代になってきています。持続可能な社会への関心の高まりもあって、ZOZOの「ゆっくり配送」のように、時間よりも配送負荷やCO2排出量の軽減を優先するようなサービスへの需要も高まることが予想されます。
● DDD佐藤尚史「優しい世界観」
「優しさ」が、やっぱり大ヒントかなと思っています。紹介しました「優しさフィルターバブル」はもちろんですが、先にご説明した「自己肯定感」のトレンドなどの全ての根底にあるのは、自分にも他人にも優しい世界観なのだと思います。
日々入ってくるニュースや、ソーシャルメディア上の根拠のない誹謗中傷などを苦手に感じる傾向ってありますよね。なので、優しさを感じられるものや、お互いを肯定しあえる関係性を促進するツールといったものが、自分の不安感を取り除いて、かつ精神防衛をするという意味で、広がりを見せてくるのではないか。これは、2025年に結構来るトレンドではないかなと思っています。

当ウェビナーに登壇したDENTSU DESIRE DESIGNは、「心が動く消費調査」という定点観測調査をベースに、社会・消費者のインサイトや、トレンド分析・ヒット分析のようなことを様々なサービスとして展開しています。人の持っている欲望を11種類に体系的に分類した「11の基本的な欲望」というものを根幹として持ち、こちら今年の3月に、時代の変化に伴う価値観の変化を捉えた形でリニューアルしています。

リリース:「電通、最新の「欲望未来指数」から消費意欲の活発化を予測 」
DDDは消費者分析・トレンド分析、その視点を生かしてマーケティング戦略の立案や、欲望基点の新商品開発プログラム「心が動く新商品開発プログラム」などのソリューションをご提供しています。ご興味を持たれた方はぜひ一度お問い合わせください。
<お問い合わせ方法>
下記のバナーをクリックし、フォームへとお進みいただき、「お問い合わせの目的」で「掲載ソリューションに関するご相談」を選択し、必要事項をご記入の上、お問い合わせください。