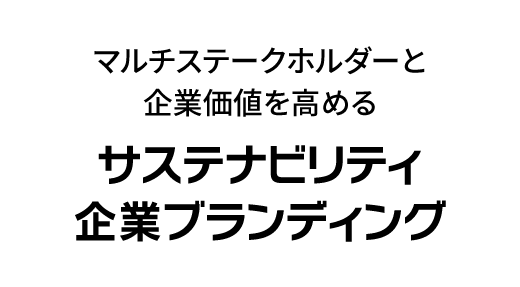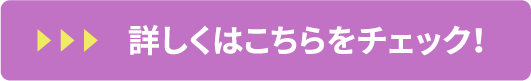サステナビリティ推進は、もはや「やってあたりまえ」の今。みなさんの会社ではどれくらい取り組みが進んでいるでしょうか?「守りの対応以上は手を付けられていない…」と感じるのも無理はありません。なぜならサステナビリティ推進には多くの経営アジェンダがあり、アジェンダごとに異なるステークホルダーや課題が絡み合っているからです。複雑なサステナビリティ推進の全体像と今やるべきアクションを効率よく見出す方法を、電通サステナビリティコンサルティング室の森がご紹介します。
PROFILE
INDEX
サステナビリティ、「笛を吹けども踊らない」問題
半数以上の企業が、推進活動に悩んでいる
サステナビリティ推進において「活動が個社レベルに止まっている、もしくは成果が出ない」という課題を感じている企業の担当者が半数を占めていることが、調査(※)で分かっています。実際に私も、サステナビリティコンサルティング室の一員として企業の方々に話をお聞きする中で、以下のようなご相談をよくお受けします。
※電通独自調査「サステナビリティやESGに関する企業の取り組み調査(2023年11月実施)」
●「現場社員との間に温度差がある」
経営層や推進室が主導となってサステナビリティ方針やスローガンを設定したものの、現場の社員からは「自分の業務には関係ない。課題が大きすぎるし、自分からは遠いもの」と思われてしまい、なかなか自走に至らない。このお悩みは、私の肌感覚でとても多いと感じます。
●「本当に買ってもらえる?」
サステナビリティに配慮した商品は、環境対応などをしている分コストがかかり、どうしても価格が高くなりがちです。商品やサービス購入の判断基準にサステナビリティを持つ消費者が増えているとは言われているものの、本当にそうした顧客がいるという確信を持てないのが企業の本音。実は、電通独自の調査*でサステナビリティ経営を支える顧客群の存在は確認できているのですが、リサイクルや回収活動などへの「顧客の参加」が重要になるサーキュラー・エコノミーを目指す企業においては、顧客の巻き込みに関する不安や課題が特に顕著です。
*サステナブルカスタマー調査データについてはこちらで詳しく解説しています
●「バリューチェーンから変えていきたいけど……」
既存の仕組みをより環境配慮型に変えていくには、時間とコストの負担も伴います。自社ではやる気があっても、サプライヤーからの理解や共感を得ることに苦労し、なかなか実現できずにいるケースもままあります。
●「企業価値向上に寄与するの?」
ESG投資家からの評価や企業価値向上につなげたいけれど、やっていることの価値をなかなか上手くレバレッジできない…といった声もあります。CSRからCSVへの進化、業界・メディア・顧客等ステークホルダーからの支持、そのための発信などがオーソドックスな課題になります。また、社会貢献活動は声を大にして言うものではないというある種の“奥ゆかしさ”を持つ企業さんもいらっしゃり、社風とバランスをとった対外発信もこのテーマに頻出する課題のひとつです。
こうしたお悩みに近しいケースをお持ちの方、多いのではないでしょうか。
整理しようとするほどに、絡み合ってしまう課題……
課題は個別に存在するのではなく、連鎖的に絡み合っている
これらのお悩みが特に難しいのは、課題が個別に存在するわけではない、ということです。一つの課題に芋づる式に他の課題がひもづくため、目の前の課題に真正面から向き合っても、すぐにまた壁にぶつかってしまうことも。
さらに困ったことに、こうしたお悩みには、それぞれ異なるステークホルダーが存在します。たとえば、企業や自治体が一体となって取り組む「脱炭素化」とサプライチェーン全体の巻き込みが大切になる「サーキュラー・エコノミー(循環経済)の構築」とを思い浮かべていただくと、課題によって重要なステークホルダーの構成に違いがあることがお分かりいただけるかと思います。アジェンダ毎に「誰と」を意識して施策を決め、限られたリソース(経営資源)のなかで「いつまでに」「何を」行うのかスコープを区切り、経営層や現場などレイヤーごとに取り組むべき課題を特定する。これらを着実に進めることが大切です。
社員、顧客、サプライヤー、投資家といった多様なステークホルダー(=マルチステークホルダー)との協業が求められるのは、サステナビリティ推進の特徴の一つ。私たちサステナビリティコンサルティング室でも、企業の取り組みを調べる中でとりわけチェックするのが「社員や顧客など、ステークホルダーを巻き込んだ取り組みになっているか」という点です。マルチステークホルダーといかに適切な関係性を築くかは、サステナビリティ推進において非常に重要な観点なのです。
まずは「誰」と「どのように」の整理から!
さて、こうした複雑な課題を前にして、何から始めればいいのでしょうか? 私たちがぜひおすすめしたいのは、課題の「関連性」と「ステークホルダー」に着目し、課題の全体像を俯瞰的に捉えることです。
「分かってはいるけれど、それができずに困っている!」、そんな推進ご担当者の方もご安心を。ここからは、複雑に絡む課題を解きほぐすためのとっておきのソリューション、「サステナビリティエンゲージメントサイクル」についてご紹介したいと思います。
目的とアクションのつながりを、人起点で可視化しよう!
「サステナビリティエンゲージメントサイクル」とは
「サステナビリティエンゲージメントサイクル」は、サステナビリティ経営の多岐にわたる課題を、生活者・地域社会、サプライヤー、従業員、株主・投資家といったステークホルダーを起点に俯瞰したモデルです。電通グループがこれまでに取り組んできた実績とノウハウをもとに独自に開発されたフレームワークで、他社と差別化された「自社ならでは」の経営アジェンダの選択とサステナビリティアクションの持続的な実行をご支援します。

上記が、多くのケースから導いた「サステナビリティエンゲージメントサイクル」の基本モデルです。サステナビリティ推進における目的(黒)、それに関わるステークホルダー(緑)、具体的なアクション(グレー)がプロットされ、サイクルの線をたどることで「誰とどんなアクションが必要か、次に何をすべきか」を俯瞰して把握することができます。
複雑に絡み合って「何から手をつければいいか全容がつかみにくい状態」だったものが、つながりで整理され一覧できる。目的達成のために、誰とどのような施策をしていけばいいのか、キーアクションの優先順位を明らかにすることができる。これが、「サステナビリティエンゲージメントサイクル」の大きなメリットです。
飲料メーカーの例で見てみると……
より活用イメージが湧きやすいように、ある飲料メーカー様のケースでご説明しましょう。
創業時から水や自然を大切にする姿勢を貫いてきたこちらの企業。サステナビリティに取り組むことがある意味“あたりまえ”だったため、経営層は「わざわざ発信すること」に消極的。一方で、現場の従業員の方々は、他社が環境に配慮した商品開発や発信を行うのを見ながら「自分たちも本気で取り組んでいることを多くの人に知ってほしい」という思いを抱え、意識にギャップが生じている状態でした。また、会社のサステナビリティに関する方針が明確になっておらず、環境活動に対する優先順位も、部署や人によってバラバラでした。
そこで、まずはサステナビリティに対するビジョンを定めることで、経営陣と従業員の認識を共有することから始めました。サイクルで見ると、まさに左下の部分です。

さて、ここでビジョン止まりにならないのがこのサイクルの活用ポイント。認識を共有したら、次は下図の紫のラインにある注力指標の設定が必要であることが分かり、同じ紫の線をたどっていけば、次に具体的な活動の検討が必要になることが分かります。そしてさらに黄色の線に派生していくと、顧客となる生活者への発信や、購入に結び付けるアクションが必要であることが見えてきます。

課題がスッキリ整理されると、ワクワクも高まる!?
「サステナビリティエンゲージメントサイクル」の効果
このように、サステナビリティ推進におけるさまざまな課題とアクションを、つながりで把握できる「サステナビリティエンゲージメントサイクル」。先の飲料メーカー様事例では、まず優先順位の高い「経営陣」と「従業員」の間のアクションから取り掛かったことで、社内の意識が統一され、次のアクションに取り掛かる際の認識のブレが少なくなりました。また、その意識統一を進める過程で役員同士・社員同士が本音で話せるようになり、「この人はこんなことを考えていたんだ」「それならもっとこうできるかも!」と社内の議論がポジティブな方向へとシフトしていきました。全体像を俯瞰できることで、企業課題と照らし合わせながら優先順位をつけることができます。それにより、次のアクションが具体的に見えてくるため、義務感からではなく、前向きな気持ちで楽しみながら挑戦できる余裕が生まれたのかもしれません。
課題整理から具体施策まで、一気通貫でご支援
繰り返しになりますが、複数のステークホルダーとの関わりが求められるサステナビリティ推進においては、「誰と」「どのように」進めるかを俯瞰的に捉えることが大きなポイントです。「今考えるべきアジェンダをうまく整理できていない」「従業員やその他のステークホルダーとの間にギャップがある」「取り組み始めたものの、次に取るべきアクションがわからない」…そんなお悩みを抱えている企業さまに、「サステナビリティエンゲージメントサイクル」はきっとお役立ていただけるはずです。
さらに電通では、こうした課題の抽出だけでなく、その企業らしいサステナビリティ施策の企画立案と実行支援、認識共有のためのスローガン開発、生活者へのコミュニケーション、さらにはサーキュラー・エコノミー推進のしくみづくりまで、それぞれのフェーズで具体的な支援もご提供しています。サステナビリティ推進に関するお悩みやご相談がありましたら、ぜひ私たちサステナビリティコンサルティング室にご相談ください。
●「サステナビリティエンゲージメントサイクル」の詳しいeBookはこちらから