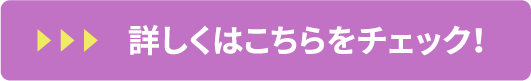コロナ禍を経て営業プロセスのデジタル化が加速し、多くの企業において営業活動の高度化・高品質化に向けた環境整備が進んでいます。
目指すのは営業部員の誰もが自社のマーケティング戦略と顧客を深く理解し高いモチベーションをもって営業活動が行えるようにすることです。
今回はその目標を実現するための重要な要素の一つ「ナレッジ共有」について大事なことをお伝えしたいと思います。
PROFILE
INDEX
営業部門が抱える課題
コロナ禍を機に、対面営業が中心であった営業部門でも、リモートワークが一気に加速しました。
リモートワークには営業部門にとっても様々なメリットがあります。リモートワークを導入することで、地理的・時間的な制約を受けずに営業部員が活動できるようになり、業務時間を有効に活用できるとともに、幅広い顧客へのアプローチが可能になります。
しかしながら一方で、リモートワークの導入には様々な課題も見られるようになりました。
進むコミュニケーションロス
営業部門の責任者の方々からは、「部下とのコミュニケーションが不足している」「部下がどのような営業活動をしているのかよくわからない」といった悩みも多く聞かれます。
また、リモートワークをうまく活用できる部員はグングンと業績を伸ばす一方で、そのノウハウや顧客から得た情報を共有する仕組みがないために営業知見の属人化が進み、営業部門全体として見たときには成果のばらつきが拡大していきます。
会社の有用な情報からの分断
会社にある様々なケイパビリティを理解していない、様々な資料がスムーズにアクセスしやすい状況にない、現場ですぐ利用できるような資料になっていないと、顧客に自社のサービスの有用性を説得力をもって説明できず、結果として受け身の営業になってしまいがちです。
人材に関する悩み
このような状況が進み、孤立に悩み離職する社員も多いようです。
また人材の流動化が進み、中途採用にかかるリソースや、中途入社社員への社員教育が恒常的に必要になり、営業部門全体への負担も増大しつつあります。
こうした状況を改善し、成果を上げるために、効果的な現場ナレッジの共有はますます重要になってきています。
営業部門のナレッジを共有することによるメリット
営業部門のナレッジには、2つの種類があると考えています。
この2つのナレッジを適切に共有する仕組みをつくることで、既存の営業部員の高位平準化、ならびに新規採用社員の早期戦力化が可能となり、営業部門全体の業績向上が期待できます。
営業現場のナレッジ共有
1つ目は、顧客から聞き出したニーズなどの情報や有効な営業活動のノウハウで、営業現場で働く一人ひとりが持っているナレッジです。
優秀な営業部員は、より効果的な顧客への接し方・情報の取り方のノウハウを持っており、それをベースにして営業活動をすることで、良い成績を上げることができます。このノウハウをナレッジとして型化するとともに、営業活動で得た有益な情報を営業部門をはじめ、社内に共有する仕組みを作ることで、営業活動の高位平準化を実現するだけでなく、研究開発など全社にとって貴重な知見を集合知化していくことができると考えています。また、横連携の仕組みをつくることで、営業部門内のモチベーション活性化も期待できます。
社内資産のナレッジ共有
2つ目のナレッジは、営業に活用すべき社内資産(アセット、研究資産)です。
例えば、自社内の貴重な研究開発の情報や、市場環境に関する情報があっても、関連各部署のサーバーにバラバラに保存されスムーズにアクセスしにくい状態、また、ファイルを開いても、すぐに活用できないような情報であると、有効に活用することができません。これらのナレッジを整理して保管し、全社で共有する仕組みを作り、いつでも誰でも活用できる状態にすることが重要です。さらにその資料が、営業の現場ですぐ使えて役に立つものにコンテンツ化されていることも重要です。このような仕組みを作り営業担当者が提案に利用できるようにすることが、競合他社との差別化につながり、ニーズを先読みした提案につながります。
昨今ではこのようなニーズに応えるためナレッジ共有のためのSaaS型の支援ツールも数多くリリースされています。
ナレッジ共有における秘訣
しかしながら「ナレッジ共有はツールを導入すれば実現できる」という簡単なものではありません。ツールを導入したり、システムを構築したりしても、利用されずに放置されているケースが多いのも事実です。
では、現場が利用したくなるナレッジ共有の仕組みにするためにはどのようなことが必要なのでしょうか。
現場の状況の深い理解とアップデートの体制づくり
ナレッジ共有を導入し、定着させ、活用してもらうには、現場担当者のニーズや業務フローを深く理解したうえで、ナレッジを抽出し、活用できるようにコンテンツ化し、アクセスしやすい仕組みを整備する必要があります。
また、ナレッジ共有の仕組みは、いったん作れば終わりというわけにはいきません。ナレッジを常に最新の状態にアップデートするのと並行して、アクセス状況を分析し、使いやすいように改善していかなくてはなりません。
進んでナレッジ共有を行う文化の醸成
ナレッジというのは、個々の営業部員にとって宝です。営業部内の部員同士が競争を強いられている環境では、他の部員は全員ライバル。自分の大事なナレッジを共有することがすなわち自分の評価低下につながりかねないため、メリットを感じられず、ナレッジ共有は進みません。進んでナレッジを共有しあう組織文化へと改革することも必要です。
この2つを同時に進めていくことにより、既存の営業部員の高位平準化ならびに新規採用部員の早期戦力化が可能となり、営業部門全体の業績向上が期待できます。

電通グループが提供する「ナレッジ共有プログラム」とは
私たち電通グループは、これまでにマーケティング領域で培ってきた「生活者のインサイト探求力」「人を動かすクリエイティブ」「マーケティングの知見」をベースに営業部門の変革を支援するプログラム「Sales Transformation For Growth」を開発し、顧客企業に提供しています。その中のサービスの一つとして、「ナレッジ共有支援」のソリューションを提供しています。
電通グループのナレッジ共有支援ソリューションは、次の3つのステップで営業部門のナレッジ共有の仕組みを構築から運用まで伴走し、現場社員のモチベ―ションアップまでつなげます。
① ナレッジの型化
優れたパフォーマンスを発揮している営業部員の行動、各種データを分析するなどして、成果要因を明確化し、暗黙知であるナレッジを抽出。他の営業部員が使えるような「虎の巻」を作成します。また、電通独自の「問いの立て方」メソッドを活用し、顧客との対話を適切に掘り下げる最適なアプローチを型化します。
② ナレッジ共有の場づくり
ナレッジ共有プラットフォームを導入し、誰でも、いつでも、どこからでもすぐにナレッジを得られる場を提供するとともに、営業部員同士で営業活動から得た情報や成功・失敗事例を共有し、互いのスキル・能力・知識を高め合えるシステムを構築します。生成AIを活用することで、営業部員の質問に即時に回答し、資料も紐づけて提示するような機能を実装することも可能です。
③ ナレッジ共有/活用に導く組織風土改革
ナレッジが適切に抽出され、現場で適切に共有/活用されるようなフローの策定と運用により、ナレッジ型化から共有までが営業部門全体に定着するような仕組みづくりを行います。また、営業担当者が自発的にナレッジを提供したくなるような評価制度の設計や、組織風土の構想・浸透までをサポートします。
営業部門のナレッジ共有ご支援事例
これまでに電通がナレッジ共有を支援した企業の事例を紹介します。
【事例1】大手メーカー様 営業社員向けナレッジ共有プラットフォーム構築支援
大手メーカー様において、営業活動における好事例の蓄積・共有を行い、営業社員のモチベーションを高め、活動を活性化させるためのナレッジ共有プラットフォームの構想から開発、浸透・運用設計までをワンストップで支援しました。最前線で働く営業社員のインタビューを入念に行うことで、ナレッジへのアクセスから活用までの導線設計を含め、真に現場社員から支持されるプラットフォームを構築・導入しました。
【事例2】ヘルスケア企業様 生成AIを活用したセールスサポートAI構築支援
国内の大手ヘルスケア企業様において、営業社員の商談データを収集・分析し、パフォーマンスの高い営業部員とそれ以外の部員の特徴差分を導出。その上で、トップセールスのナレッジを抽出して作成した「虎の巻」をもとに、効果的な営業アクションを対話型生成AIで教育する「AIトレーナー化」を現在試行しています。
営業部門を成長ドライバーへ

私たち電通グループは、「営業部門は企業の成長ドライバーになる存在である」と捉えています。
「Sales Transformation For Growth」は、単に「製品/サービスの売上を伸ばす」だけでなく、営業部門の一人ひとりが、自らの営業活動を通じて全社の売り上げや成長、ひいては社会全体の活性化に貢献し、営業部員として成長する意識と実感を得てもらうことを目的として開発されました。
そのプログラムの中のソリューションの一つである「ナレッジ共有支援ソリューション」は徹底的なユーザー視点で設計・検証し、頻繁に訪れたくなるプラットフォーム開発から、積極的に共有したくなるような仕組み作りや組織風土改革まで、構想-実装-運用をワンストップで伴走します。必要に応じて運用人員のご提供も可能です。
「ナレッジ共有支援ソリューション」及び「Sales Transformation For Growth」について、詳しい情報はダウンロード資料やソリューション紹介ぺージをご覧ください。