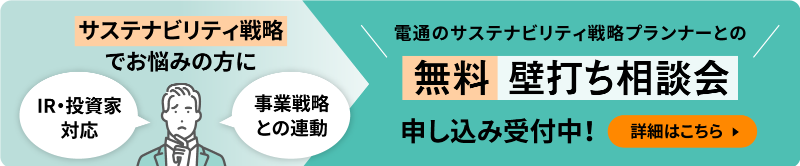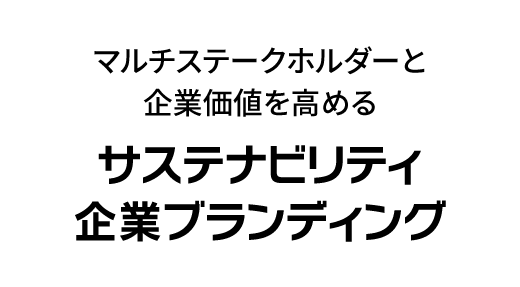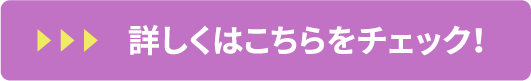サステナビリティ経営に対する意識の高まりを受け、財務以外の情報を積極的に開示する企業が増えています。今やそうした非財務情報は、ともすれば財務資産以上に企業価値を左右し得る重要なファクター。情報の価値を正しく見極め、サステナビリティ経営に活かしていきませんか? 電通サステナビリティコンサル室の蟹江が、非財務情報を分析する独自ソリューション「非財務価値サーベイ」についてご紹介します。
PROFILE
INDEX
近年、注目が高まる非財務情報
そもそも非財務情報とは?
企業が外部に開示する情報は、大きく「財務情報」と「非財務情報」に分類されます。財務諸表で開示される定量的な情報=財務情報に対し、数値化できない定性的な情報が非財務情報。これを読んでいる皆さんには言わずもがなかもしれませんが、その中身をもう少し詳しくおさらいしましょう。
非財務情報には、主に以下の5つの資本に関する情報が該当します。
1. 製造資本
2. 知的資本
3. 人的資本
4. 社会・関係資本
5. 自然資本
※参考:国際統合報告評議会(IIRC)「国際統合報告フレームワーク(IIRCフレームワーク)」における分類
堅い言葉が使われていますが、つまり商品開発力や技術力、経営者の能力の高さや経営方針、社員のモチベーションの高さやスキル、優良な仕入れ先や得意先との関係性、そして事業の環境貢献度などが、非財務情報の具体的な中身になります。
投資だけじゃない! 非財務情報が求められる理由
今、企業経営においてこの非財務情報が大きな意味を占めるようになっています。その背景にあるのは、世界的なサステナビリティ意識の高まり。サステナビリティ経営の重要性が増すなか、社会課題に対する取り組み姿勢などの情報開示が、投資家たちの間で強く求められるようになったのです。
また、そうした非財務情報が就職先を選ぶ基準になったり、商品購入や契約の決め手となったりと、投資以外の局面でも広く重視されるようになっています。グローバルで見てみると、米国市場(S&P500)の企業価値における無形資産比率はなんと90%(2020年)にも(※)!企業の競争力の源泉が、有形資産から無形資産にシフトしていることがよく分かります。
※出典:内閣府「知財・無形資産の投資・活用戦略の開示およびガバナンスに関するガイドラインVer1.0」
見えない情報だからこそ、その価値が判断しづらい
日本は非財務情報の活用が遅れている
日本でも2023年3月期から、有価証券報告書でサステナビリティ情報の開示が義務付けられました。それを受け、近年「統合報告書」や「サステナビリティ報告書」等で非財務情報の公開を行う企業が急増しています。ところが、日本企業の企業価値に占める無形資産の割合は、欧米と比べて相対的に低い(※)ことをご存じでしたか?
※出典:内閣府「知財・無形資産の投資・活用戦略の開示およびガバナンスに関するガイドラインVer2.0」
その要因として、多くの日本企業が「非財務活動と業績の関係性」を認識できていないことや、多種多様なサステナビリティテーマの中から有望なものを見いだせていないことなどが挙げられます。実際に統合報告書などで情報公開に取り組みながらも、実は“その情報を公開する意義”や“自社の非財務情報の価値”をきちんと把握できていない……なんて人も多いのではないでしょうか。
数値化の難しさが、情報活用のネックに
非財務情報は、財務データと違って簡単には数値化することができません。数値で表せない分、わかりやすい指標が設けづらく、一般的な判断基準も定まっていないことがしばしば。そのため、「やってはいるが、次に打つべき手がわからない」「企業価値を高めるために今後どこに注力したらいいかわからない」といった状況に陥り、義務的な非財務情報開示に留まってしまっているケースが多くみられます。
重要なのに、数値化できないから価値がわからず、活用できない。それが非財務情報を取り巻く日本企業の現状ですが、そのために自社のサステナビリティ経営の可能性を狭めてしまっているとしたら、非常にもったいないことです。
「非財務価値サーベイ」で取り組むべき“高価値活動”を発見しよう
「非財務価値サーベイ」とは
そうした課題を解消するためにまず必要なのは、ずばり「非財務情報価値の正確な分析」です。高度なデータ分析を通じて自社の非財務情報を客観的・相対的に評価することで、自社の立ち位置が明確になり、非財務情報を経営に活かす筋道や方向性がわかるからです。
電通では、そうした考えに基づき、2023年から「非財務価値サーベイ」の提供を開始しました。これは、企業の財務データ・ESG評価データ・イメージデータ・従業員クチコミデータという4種類のビッグデータを掛け合わせ、企業価値に与える影響を分析することができる電通独自のソリューションです。

「非財務価値サーベイ」でわかることとは
「非財務価値サーベイ」を使うと、例えば以下のような問題についての評価や因果関係を明らかにすることができます。
1. ステークホルダー評価の問題
【問題】どの活動がどのステークホルダーに響いているのかがわからない
【分析できること】ステークホルダーごとの評価を判定
2. 競争優位評価の問題
【問題】自社の取り組みが競合と比べて優れているのかわからない
【分析できること】業界平均/競合他社との比較により、貴社の強みと弱みを明確化
3. トレンド把握の問題
【問題】今後、取り組みを見直そうにも、どう見直してよいかわからない
【分析できること】ステークホルダーの評価向上につながりやすいサステナビリティ活動を特定
4. 社内合意の問題
【問題】当事者ごとの意見が様々で、議論がかみ合わず合意できない
【分析できること】データ分析結果を基に経営者と従業員が現状を同じ目線で振り返り、今後の方向性に合意を取る
ポイントは、分析によって現状把握をするだけでなく、現状を踏まえたうえで「今後重点的に取り組むべき課題は何か」までしっかり導くことができる点です。サステナビリティ経営でこれから問われるのは、いかに「企業価値への貢献度の高い活動」に取り組むか。サーベイによって企業価値貢献を見える化することで、活動の取捨選択ができるようになります。
進むべき道を発見し、合意を取るためのファクトデータに
例えば、サステナビリティにおいて業界内でトレンドとなっている活動があるとして、そこへの取り組みが不十分な企業に対して「こういうテーマで活動を行えば、今後成果が生まれるのではないか」といった仮説をデータに基づいて提示することができます。
あるいは先進的な取り組みを行う企業に対しては、まだどこも手を付けていない次の領域を見つけ出し、新たな可能性を提示することも可能です。実際に取り組むためには信頼できる分析データや評価がないと社内で合意が取りづらいものですが、そうした場合のファクトデータとしても、「非財務価値サーベイ」の分析結果が納得材料となるでしょう。
こんな企業こそ、ぜひ「非財務価値サーベイ」を
活動内容の検討からステークホルダーとの関係構築まで
「非財務価値サーベイ」は、サステナビリティへの取り組みレベルに関わらず、幅広い企業さまにご活用いただけるソリューションです。
もし自社のサステナビリティ対応が遅れている自覚がある場合、そのままでは今後の経営リスクが高まる一方です。そうした場合は早急に「非財務価値サーベイ」の診断を受け、自社の立ち位置をまずしっかり把握することをおすすめします。サーベイとセットで、今後の活動を検討するワークショップをご提供することもできますので、分析からアクションプランの策定まで一貫して取り組んでいただけます。
企業によっては、データ分析によって注力すべきサステナビリティテーマが分かっても、実現が難しいケースもあります。そういう場合には、どうすれば実現できるのか、因数分解をするように課題を振り分けていき、道筋を探るお手伝いができるでしょう。
また、サステナブルな事業をマネジメントするには、多岐にわたるステークホルダーからの理解や協力が欠かせません。幅広いステークホルダーの評価を明らかにして、今後のコミュニケーションや関係づくりを改善していきたいという企業さまにも、このサービスをぜひ活用していただきたいです。
……といったように、サステナビリティの取り組みや今後の進め方に悩んでいる企業のみなさまに、さまざまな角度からお役に立てるはずです。自社の非財務資本の価値やその活かし方にお悩みの方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。
●「非財務価値サーベイ」を詳しく説明したeBookはこちらから