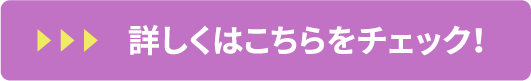定員を大幅に超える応募者数、参加者全員が無遅刻無欠席、実施後に社員の多くが手ごたえを実感……。そんな活気あふれるワークショップが、2023年初夏、ファンケル総合研究所にて実施されました。
これは、同研究所のビジョンを新たに策定するためのワークショップ。電通の未来事業創研が伴走し、当サイトでもご紹介しているフレームワーク「Future Craft Process」を用いて、つくりたい未来の可視化とビジョン構築を行いました。
大手企業の研究開発部門が、今あえてこのプロジェクトを行った狙いとは? そして、高いコミットメントと満足を引き出した秘訣とは? ファンケル総合研究所の若山和正所長と未来事業創研ファウンダーの吉田健太郎に、編集部が取材しました。
⇒未来構想支援プログラム「Future Craft Process」の概要資料はこちら
PROFILE
INDEX
未来にプラスの価値を生み出したい。その考えに共鳴して
最初に、ファンケルさまにおける総合研究所の役割について教えていただけますか。
若山所長:ファンケルグループは “世の中の「不」を解消したい”という想いを原点に、「もっと何かできるはず」という経営理念を掲げて40年間独自のポジションを築いてきた企業です。
大きな強みは、研究から製造、販売まで、自社で一貫しておこなっていること。お客さまの課題や声を正しく捉え、それに見合った研究を行い、製品を提供するという意味では、研究所はまさにグループの一丁目一番地。美と健康における“不”の解消を具現化することが、私たち総合研究所の役割です。

研究開発部門として独自のビジョンを掲げようと思われたのはなぜでしょうか?
若山所長:私が研究所所長に就任したのが2022年10月なのですが、研究所の役割について改めて考え直したとき、未来の世の中に起こり得る「不」の解消にも目を向け、少し視点を変えてアプローチをしていかなければと思ったことが発端です。
というのも、実は所長になる前は事業戦略やマーケティングを担当しておりまして、未来を予測してから取り組むべきことを考えるというのが基本の考え方として染みついていました。しかし製販一体で事業をしていると、どうしても今や来年といった短期的な視点に陥ってしまいます。それは研究所にも言える課題ですが、研究は本来、一番長期的な視点を持って取り組まなくてはならない部門。ビジョン構築によって研究員たちも視点をもう少し未来に向けさせ、「この研究は何のためにやっているのか」「今後どこに」といったように、研究開発の意味や今後取り組む領域を明確にしたいと考えました。

詳しくありがとうございます。それで、つながりのあった電通にお声がけいただき、未来事業創研とのプロジェクトが始まったんですね。
吉田:そうですね。でも実はミッション策定の一年前に、ファンケルさんの別の事業部と勉強会を開催しているんです。そこで美容領域以外の取り組みや社員の方々の思いをお聞きする中で、“「不」の解消”という言葉に僕自身が非常に共感しました。
「不」の解消というのは、何かに負けているマイナス状態からゼロにする「負」の解消ということではなく、あらずの状態、つまり“こうありたいができない状態をなくす”という発想ですよね。ゼロに近づけるのではなくプラスを生むという考え方が、ファンケルさんと未来事業創研の大きな共通点で、それが今回のプロジェクトにつながった一番の理由じゃないかと思います。

研究員が主体となる、ワークショップ形式のプロジェクトをご提案
プロジェクトに際し、未来事業創研からはワークショップを中心とした「Future Craft Process for ファンケル総合研究所」というプログラムを提案しています。このプログラムを提案されたのはなぜでしょう?
吉田:「Future Craft Process」は、未来の社会課題と人々の思いが重なったところに企業価値を見出していくということがベースになっていて、まずその基本的な思想がファンケルさんの目的にマッチしていました。

0~3までのステップの中で、重要な位置を占めているのがステップ2の「つくりたい未来の可視化」です。ビジョンをいきなり言語化するのではなく、まず目指す未来の姿を具体的に描くことで、「何のために研究をやっているのか」をよりイメージしやすくする狙いがあります。
そしてこのフレームが、「社員参加型のワークショップ形式」を取っていることもポイントです。上から一方的にビジョンを投げられても現場の人たちはなかなか自分ごと化しづらいですし、社員の皆さん一人ひとりが自分の思いや考えに気づく場を作りながらビジョンを構築していくことが有効な手法だと僕らは考えています。
ワークショップ形式を取ったことが大正解で、メンバー募集の段階で定員をはるかに超える人数の応募があったとか……
若山所長:そうなんです。うちの研究員は、アイデアを発想することが好きなメンバーが多いんです。それに普段は各部門に分かれて研究に打ち込んでいるので、なかなか横とのコミュニケーションを取る機会も少なく、より興味が湧いたのだと思います。メンバー選考では、プロジェクトへの意欲や実現したいことなどを書いたプレゼンシートを提出してもらいました。
吉田:他社で実施しても、なかなかプレゼンシートまで提出していただくことってないんですよ。当初は4チームで予定していましたが、応募が多いので倍の8チームに増やし、ワークショップ参加メンバー以外にもサブメンバー、オープン参加メンバーと3階層に分けたほど。
チーム構成も、部門や年齢が被らないようかなり時間をかけて検討しました。また、私たちのワークショップでは、グループワークの際に必ず未来事業創研のメンバーがグループファシリテーターとして各グループに参加します。クライアントの方だけのグループになると先輩・後輩といった関係性や、役職などの立場によって発言や影響力に偏りが生じやすいためです。
「できそうな未来」から「つくりたい未来」へ、思考をジャンプさせるコツとは?
それではステップごとに取り組みを振り返っていきたいのですが、まずステップ0では「自社らしさの分析」をされるんですね。これは企業自身で行うのですか?
吉田:はい。まずは自社の持っているリソースを自分たちで棚卸しして、武器として認識しましょう、というのがステップ0です。といっても、そこから“フォアキャスト型”で未来を考えていくのではありません。その後考える「つくりたい未来」から“バックキャスト”したときに、活用できるシーズやファンケルらしさを確認するための材料として整理しておくイメージです。
棚卸しができたら、今度はステップ1の「未来課題インプット」です。オンライン形式で、テーマごとに未来の変化や技術の進化をレクチャーされたとか。
吉田:現在は「未来ファインダー100」としてリリースさせていただいているものなんですが、未来情報を100のテーマに分けてサマライズしたツールを用いました。ただ当時は100テーマではなく72テーマの構成でした。その中から、ファンケルさんの事業に関連するテーマを選んでインプットさせていただいたのですが、ファンケルさんの事業領域は「美と健康」なので、関連するテーマの幅がものすごく広くて……。特に食領域はほとんどのテーマが関係することや、最近はフードテックはじめテクノロジーの進化が激しいですし、テーマ選びはファンケルさんでもだいぶ悩まれたと思います。
若山所長:本当にその通りで、あれもこれも知りたいことばかりで、どのテーマを選択するのかメンバーで投票をして選びました。インプットが終わった後、メンバーと話をしたら、やはり研究者・技術者として、自分の領域外でどんなテクノロジーが生まれているのか、どんな課題にどのように対処してるのかを知ることはすごく勉強になったと言っていましたね。
 未来課題インプットツールのイメージ
未来課題インプットツールのイメージ
研究開発部門の方はテクノロジーへの好奇心が強い方が多そうですし、このインプットで未来に向けた視野がぐっと広がりそうです! その後、ステップ2でいよいよ具体的な未来の構想に入っていきますが、アイデア発想は順調でしたか?
若山所長:それが……なかなか苦戦していました(笑)。やはり研究者という職業柄、どうしても実現可能性を意識してしまうんですね。論理的に自分が理解できる範囲での発言や発想になって、そこからなかなかジャンプできない。ステップ2のワークショップは3日間行いましたが、途中で吉田さんに相談して。
吉田:1日目が終わった時点で、未来事業創研のファシリテーターたちにもっと話を引き出すよう伝え、さらにメンバーの皆さんにも「できそうな未来じゃなくて、つくりたい未来を考えよう」ということを改めてお話ししました。
 実現可能性にとらわれず、アイデアをいかにジャンプさせられるかが課題となったワークショップ
実現可能性にとらわれず、アイデアをいかにジャンプさせられるかが課題となったワークショップ
実現可能性や現実的な部分を意識してしまうのは、製品化や販売まで視野に入れなければならないメーカー研究者ならではの課題かもしれません。そうした発想の枠を、未来事業創研ではどのように外していったのでしょうか?
吉田:「つまんないアイデア浮かんじゃったんですけど」と気にせず言える雰囲気を、ファシリテーターが率先して作ることですね。具体的に言うと、メンバーの意見を肯定する・具体例を出す・言い換えるの3つがポイントです。どれだけぶっ飛んだ非現実的なアイデアでも、否定せずにまずはファシリテーターが横から肯定する。そこから「もうちょっと具体的に考えてみると……」と現実に寄せていった方が、同じ結論になったとしても検討プロセスに大きな差があると思うんです。
なるほど! 普段のアイディエーションでもとても参考になるテクニックですね。ちなみに、ワークショップで「これは結構(発想が)飛んでいるな」と思うアイデアはありましたか?
吉田:「65歳からのピチピチ♥ラブレボリューション」という、シニアでもキュンキュン恋愛したいという思いを描いた未来アイデアが印象的でしたね。“シニアでキュンキュン”なんて、普段の研究者の方からしたら「なんだそれ?」ってアイデアだと思いますけど(笑)。でも、その願いを叶えるために“老化への諦め”という「不」の解消を目指するのだと考えれば、ファンケルさんの経営理念にちゃんと即しています。
若山所長:研究者としてではなく、個人としてそういうノリや発想が好きなメンバーも実はたくさんいるんです。それをワークショップで解放できたのはとてもよかったですね。
 完成した未来ライフピースの一つ、「65歳からのピチピチ♥ラブレボリューション」。
完成した未来ライフピースの一つ、「65歳からのピチピチ♥ラブレボリューション」。
美と健康の先にある充実したシニアの暮らしがいきいきと描かれている。
未来を描くことで再確認した、自分たちの原点とあるべき姿
そうしたアイディエーションを経て、最終的には未来構想がプロのイラストレーターによってビジュアル化され、24ものライフピース(=つくりたい未来)が完成しました。それらをご覧になって、何か気づいたことはありましたか?
若山所長:テーマやライフステージごとにつくりたい未来が可視化されたのを見て、事業領域である美と健康というのは、結局“手段”であって、私たちが本当に目指しているのはその先にある暮らしや幸せなんだ、ということが非常にしっくりと理解できました。
化粧品やサプリメントを作ることは私たちの業務の中心ですが、それは、夢や目標を叶えるために美と健康がとても重要な手段だからであって、決してそれ自体が目的なのではありません。そしてこれは、ファンケルが創業以来目指してきたことそのものなのです。
 コミュニティエリアに掲示された、ファンケル総合研究所の「つくりたい未来」
コミュニティエリアに掲示された、ファンケル総合研究所の「つくりたい未来」
未来を可視化したことで、自分たちの原点と現在、そして未来がつながったんですね。そこからビジョンを言葉でまとめていくのは、どのように進められたのでしょうか。
吉田:ビジョンの言語化は、これも未来事業創研の独自フレームを使って「研究所のミッション(役割)」「未来課題」「つくりたい未来」「人々が望む状態」を構造化してから文章に落とし込みました。一度こちらで言語化した案を作成してご提案し、正直なご意見をいただきながら調整していきましたが、修正の方向性や内容で迷うことはありませんでしたね。
若山所長:考えや想いを深く掘り下げることなくビジョンをつくってしまうと、どの会社でも言える、会社名が変わっても誰も気づかないようなものになってしまい、ファンケルらしい“におい”がなくなってしまう。でもこうしたプロセスを経ることで、自分たちが守るべきものが原点から未来まで構造的に理解できましたし、これからの研究所の在り方を考えていくうえで本当に指針になったという気がしています。
ちなみに当初はビジョン策定だけを予定していましたが、実際にプロジェクトをやってみると、これをより具体的に機能するかたちにも残したいなと思いました。そこで、行動指針「ファンケル総合研究所 大切にしたい心構え」も合わせて策定しました。
 完成したビジョンと心構えは、研究所のエントランスにも掲げられている。
完成したビジョンと心構えは、研究所のエントランスにも掲げられている。
研究開発部門にこそ注目していただきたい、未来という手段の有用性
今日は本当にたっぷりとお話をお聞かせいただき、ありがとうございました。最後に、プロジェクトを振り返って一言ずつお願いします。
若山所長:プロジェクトを実施してから約1年。研究員全員にビジョンが浸透し定着するにはまだ時間がかかると思いますが、「自分たちの研究って何のためにあるのか」「自分は未来にどうありたいのか」という意識は着実に芽生えてきて、研究員の行動や提案にもそれが表れているなと実感しています。去年一年間で、ビジョンの明確化とそれに基づく戦略・研究テーマの検討ができたので、今年は次のステップとして、取捨選択しながら実行に移していきたいですね。
電通さんと協業できたこともよかったです。自分たちが見ている範囲や深さ以外のところから「こういう視点もあるんじゃない?」と投げかけてくれることも大切ですし、今まで使っていなかった思考のスイッチを外から押してもらえて、非常に有益な機会になりました。

吉田:逆に僕らとしては、皆さんの視野や気づきをいかに広げるかという意識をより強く持ったプロジェクトになりました。皆さんはプロとして自分の研究分野に誇りを持って仕事をされています。その価値をさらに広げることが僕らの役目。企業を主軸に、僕らが横軸となって、今後もしっかりプロジェクトに臨んでいきたいと思います。
また、今回の経験を経て、ファンケル総合研究所さんのような研究開発部門と我々の相性がとてもいいことも実感しました。長期視点での研究開発を目指しているBtoB企業や研究開発部門へのご支援に、これからは力を入れていきたいですね。
つくりたい未来を描くことで、日本の開発やものづくりがもっとワクワクするものになってくことに期待したいですね! 本日は、どうもありがとうございました。

ウェブ電通報では、実際にワークショップに参加された方の座談会記事を掲載中です。
是非あわせてご確認ください。
開発・研究の“核”を見つめ直す。ファンケル総合研究所「つくりたい未来」へのビジョン策定
ソリューションの詳細説明会やお悩み相談会も随時開催しておりますので、是非お気軽にご相談ください。→ お問い合わせはこちら