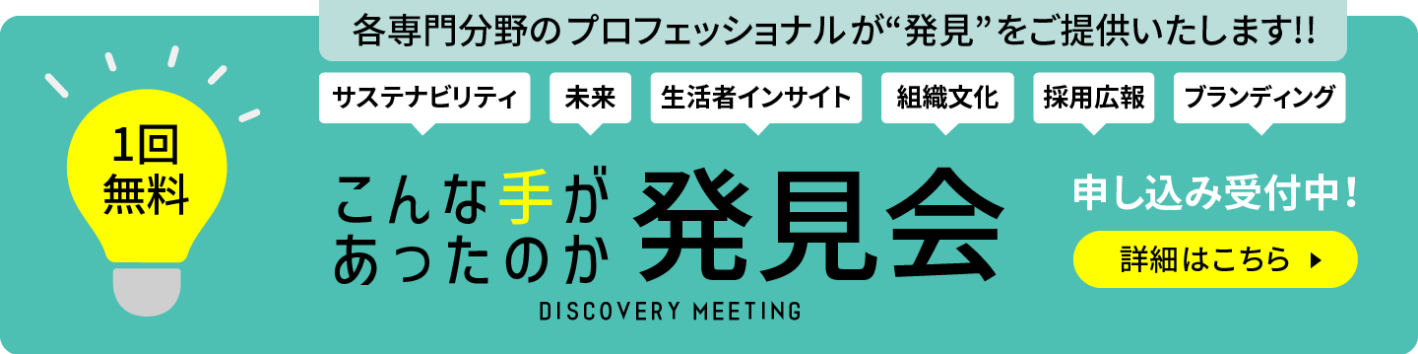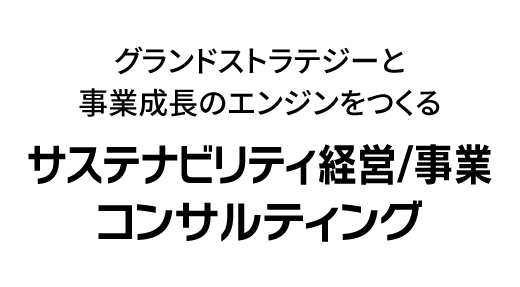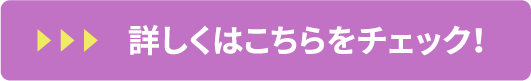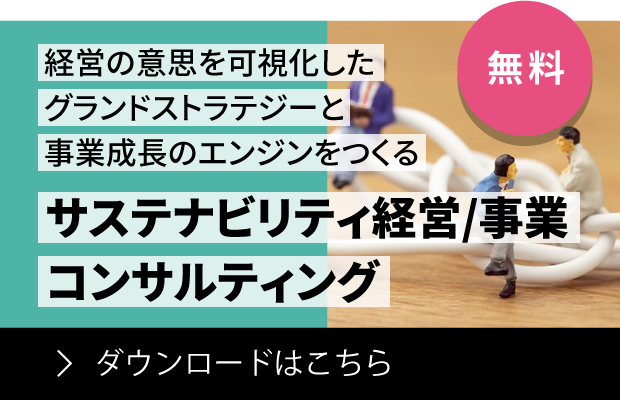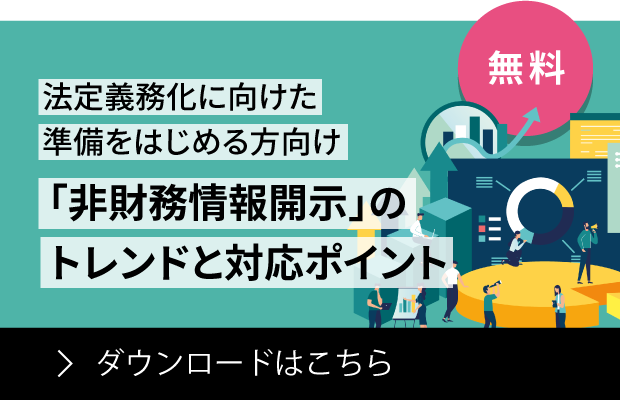サステナビリティは対応すべき義務というだけではなく、“企業価値を向上させるチャンス”になり得るものです。企業経営にクリエイティブディレクターが伴走する本ソリューションについて、狙いや他社サービスとの違いを電通 サステナビリティコンサルティング室の小野がお話しします。
PROFILE
INDEX
電通のサステナビリティ経営/事業 コンサルティングとは?
「戦略×クリエイティブ」でサステナビリティを事業成長のエンジンに
電通の「サステナビリティ経営/事業 コンサルティング」は、企業のサステナビリティ経営や事業を、戦略の立案から実行まで一貫してご支援する統合型のコンサルティングサービスです。私は、このサービスを統括する「戦略クリエイティブディレクター(戦略CD)」という立場にいます。
サステナビリティ専門家や経営コンサルタントのような肩書でないのはなぜ?と思われるかもしれません。サステナビリティ経営を考えるためには、「戦略的な視点とクリエイティブな視点を併せ持つこと」そして、「課題の解き方や答えを最初から一つの型に定めずに、課題ごとに最適な答えを探ること」、それによって「統合的に課題を解決すること」が重要な意味を持ちます。その意味が「戦略CD」という言葉に込められています。
少しイメージしづらい部分があるかもしれませんが、このブログ記事では、そんな視点でお話をさせていただければと思います。
シームレスな発想で人が動く
私は電通に入社して最初の10年、戦略プランナーとして、企業のマーケティング戦略支援の仕事をして、その後10年はクリエイティブとして、企業の経営者の皆さまと直接対話する企業価値向上プロジェクトに携わる機会が増えていきました。クライアントの経営課題と向き合いながら、同時に生活者の気持ちがどうしたら動くのかを考えるという、シームレスな発想が自分の強みです。
「サステナビリティ経営」には、まさにこの「シームレスな発想」が不可欠と感じています。多様な専門性やリソースを駆使して、どのように「人(ステークホルダー)が動く戦略」にしていくか、そのビジョン策定と実現が企業に求められているためです。
サステナビリティ経営には今、何が求められているか?
「シームレスな発想」が必要な背景
サステナビリティの課題の1つは、ステークホルダーの複雑さです。事業や商品・サービスのコミュニケーションでは、生活者や特定ターゲットに向けた戦略を考えるのに対して、サステナビリティにおける企業コミュニケーションは、発信する相手がお客様だけでなく、株主や協業先、そして社内や地域住民など実に多様です。相手に合わせて別々に対応するのではなく、異なるものをつなげて理解する「シームレスな発想」が強みになるのはこのためです。
人を動かす「求心力のあるアジェンダ」
もう1つの課題は「やらねばならない」という義務感のもとで、つい、サステナビリティの取り組み自体を目的化してしまいがちではないか? という点です。「サステナビリティ」という言葉が世界中に浸透し、情報開示を求められる中で、企業のみなさまは強い責任感・使命感のもとに取り組まれています。その中でつい、達成可能な目標や限られた専門手法にこだわるあまり、発想が狭まり、いつの間にか手段が目的化してしまうのではないでしょうか。
本来、サステナビリティは「社会、そして企業や事業をより良くするための手段」のはずです。ですので、私たちはサステナビリティをもっとポジティブに活用できる/活用すべきものだと考えています。実際に、お仕事をご一緒している経営者の方々はそうした前向きな発想をお持ちです。企業価値と直結するものだからこそ、本来の目的を忘れず、前向きにサステナビリティを捉えていらっしゃるのだと思います。
サステナビリティをポジティブに捉え、多様なステークホルダーを巻き込む求心力の高いアジェンダにして掲げ、そこに向かって自社の強みを生かしながら、仲間とともに良い社会を目指していく。そうしたムーブメントを生み出し、広げていくことができれば、多様なステークホルダーを巻き込めて、日本のサステナビリティ経営がもっと活性化するはずです。
サステナビリティの課題への向き合い方

変革の前の「探索」アプローチが大切
これまでのコンサルティング経験から、企業のみなさまからのご相談には大きく3つの入り口があることが見えてきました。
1つめは、経営の立て直しが必要で、事業や企業の変革を手伝ってほしいというもの。
2つめは、変革の方向性は定めたので、それを社会との良好なリレーションにつなげたいというもの。
そして3つめは、良い未来をつくるためにそもそも何を考えていけばよいかという、変革の前にある「探索」から手伝ってほしいというものです。
これらすべての入り口から解決のお手伝いをさせていただいていますが、特にお役に立てるのは、3つめの「探索」からのアプローチです。 「探索」は、社会がどう変わっていくのかを市場ベースで見つめるだけでなく、それらの情報をどう捉え、つなげ、マルチステークホルダーの視点で発想できるかに取り組むことが求められる仕事です。まさしく、サステナビリティ課題解決に向けて本質的な、ロジックだけではない、クリエイティビティが必要になるアプローチです。
こぼれ落ちそうなものを拾い上げる、「N=1」の視点を
私たちはつい過去の成功事例や業界の常識の延長線上に未来を描きがちですが、それでは限界があります。これまでにない未来を描くには、数字で示された大きな傾向だけでなく、例えば地方の「意志ある誰か」が始めた小さな取り組みの中に可能性を見出せるか、自分の周りの人が日頃感じているちょっとした不安や課題感を拾えるかといった、「N=1」 の視点が欠かせません。
マーケティングとクリエイティブ、異なる言語の中でこぼれ落ちそうな、人の心を動かすものを拾い上げ、対話を通して変革や企業価値向上に活かしていく。「N=1」 の視点のコミュニケーションの積み重ねが、最終的には事業成長や企業価値の期待値の向上につながります。電通のサステナビリティ経営/事業 コンサルティングを長年継続いただける理由は、この積み重ねによって創り出された戦略が具体的な成果をあげているからです。
サステナビリティの課題を解決する、電通のアプローチ
「探索」に寄り添い、必要なものが見えたらそれを統合的に具現化する
私たちはこうしたサービスを、クライアントに伴走しながら提供したいと考えています。
冒頭で、サステナビリティ経営には「課題の解き方や答えを最初から一つの型に定めずに、課題ごとに最適な答えを探ることが重要」だと申し上げました。もちろんサステナビリティ経営に必要な専門知識やフレームワーク、基本プログラムは取り揃えていますが、探索の先にどんな答えや課題があるのかは未知数ですから。企業にとっての理想的な形を常に探り続けているという状態こそが、私たちの伴走支援です。
探索する中で必要なものが見えてきたら、それを統合的に具現化します。それは電通ならではの強みです。「企業ならではのサステナビリティの捉え方をコンセプト化する」、「そのコンセプトを効果的な形で世の中に届ける」、「社内に浸透させるためのインナー施策を立案する」、「具体的な事業や商品へと落とし込む」……。ときにデジタル・PR・IRなど様々な専門性を持つチームをつくって連携し、電通グループの多彩なリソースを活かしたワンストップのご支援を提供できます。このフレキシビリティの高さは、ぜひ企業様にご活用いただきたい我々の強みだと思います。
前向きになれる“創造的な対話の場”
課題の多いサステナビリティですが、経営者の方々と未来にむけた対話をするとき、おのずと自分自身も明るい気持ちになっていることがよくあります。そして最近、実はそれが何よりも大切なことではないかと感じています。「貴社の経営をコンサルティングします」という堅い向き合い方ではなく、もっとフラットに、柔軟に、「どうすればより良い未来が来るのか?」を一生懸命話し合う。そんなポジティブで創造的な対話の場をご提供していけたらと思いますので、ぜひこのソリューションにご期待いただければと思います。

今回のブログに登場した「戦略CD」がコアの役割を担う、電通のサステナビリティ経営/事業 コンサルティングは、クライアント専属の専門チームをつくり、戦略立案から実行まで責任をもって伴走するサービスです。
サステナビリティの国際潮流や社会情勢を踏まえた提言はもちろん、それに基づく事業ドメインの再定義や、投資家・従業員を含むマルチステークホルダーとのリレーション構築、事業開発、人材・組織開発の支援など、さまざまなサステナビリティ経営/事業の意思決定を伴走支援します。
また、サステナビリティの複雑性について経営者の方々と議論し、複雑に絡み合う組織事情や経営戦略を深く理解した上で、従来分断されがちだったマーケティングとクリエイティブをシームレスにつなぎ、戦略の立案から実行まで一貫してサポートします。
シームレスな発想のもとに人が動くグランドストラテジーの推進に伴走する「サステナビリティ経営/事業 コンサルティング」にご興味のある方は、ぜひ下記にお問い合わせください。