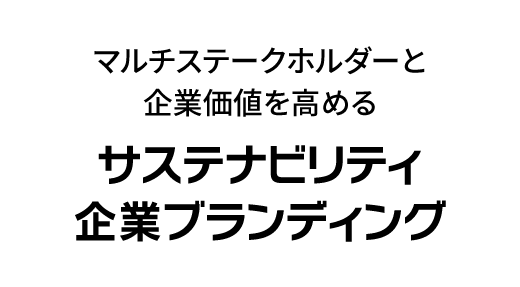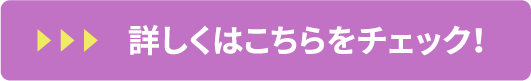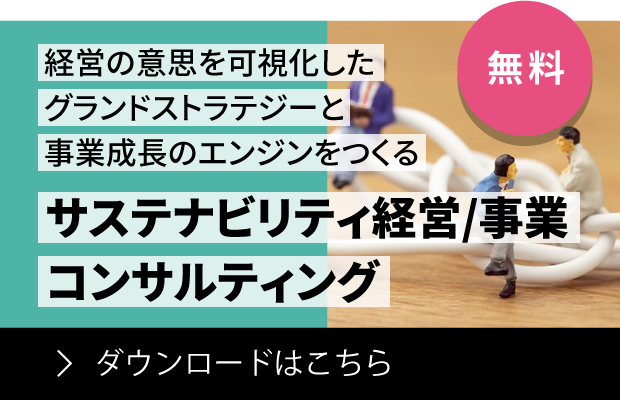2027年、有価証券報告書における「非財務情報」の開示が、大規模上場企業から段階的に義務化されます。これまで任意で行われてきたサステナビリティや人的資本の情報開示は、今後企業価値を左右する“共通言語”となっていくでしょう。
一方で、「そもそも非財務情報とは何か」「どこまで開示すべきか」「どう伝えればよいか」といった悩みを抱える企業も少なくありません。
本記事では、非財務情報開示の基本と企業がつまずきやすいポイントを整理しながら、効果的な開示を進めるための一般的アプローチ、そして電通が支援する実践的な取り組みを紹介します。
PROFILE
INDEX
2027年、有価証券報告書で「非財務情報」開示が義務化へ
2027年以降、日本では大規模上場企業から順次、「非財務情報」の開示が有価証券報告書で義務化される見通しです。これは、日本版サステナビリティ開示基準(SSBJ)による制度整備の一環で、国際的なサステナビリティ報告基準(ISSB・CSRDなど)との整合を図る動きの中で位置づけられています。
従来、サステナビリティ報告書や統合報告書などで任意に開示されてきた非財務情報が、今後は財務情報と並列で「企業価値を構成する要素」として公的開示を求められるようになります。開示対象は、環境(E)、社会(S)、ガバナンス(G)に加え、人的資本・知的資本・サプライチェーン・人権対応など、多岐にわたります。
この流れは、単なる制度対応ではなく、「企業がどのように価値を生み、持続的に成長するか」をステークホルダーに説明する責任の拡大を意味します。財務情報中心の開示から、「未来の価値をどう創るか」を語る時代へ──2027年はその大きな転換点となります。
※出所:金融庁「サステナビリティ情報開示に係る動向」(2025年6月19日)/SSBJ基準適用スケジュールより
非財務情報とは?──3つのQ&Aで基本を押さえる
Q1. 非財務情報とは?財務情報との違いは?
「非財務情報」とは、財務諸表などの数値データでは表しきれない、企業の持続的な価値創造に関わる情報を指します。
人的資本(従業員のスキル・多様性・エンゲージメント)、知的資本(技術・ブランド・ノウハウ)、社会的資本(地域や顧客との信頼関係)などが含まれます。(※1)
財務情報が「過去の成果」を示すのに対し、非財務情報は「未来の可能性」を伝えるもの。企業の“見えない資産”をどのように活かして成長していくかを示す重要な要素です。
※1:IIRC「International Integrated Reporting Framework(統合報告フレームワーク)」で示される“Six Capitals(6つの資本)”の概念に基づく。
Q2. どんな内容を開示すればいい?
非財務情報の開示対象は、ESG に限らず、企業の価値創造に関わる「財務では測れない領域」全般を含みます。具体的には、パーパスや中長期戦略、価値創造プロセスといった経営の考え方に加え、人材・ブランド・技術・組織文化・パートナーシップなどの無形資産、そして従業員エンゲージメントや顧客満足度などの非財務KPIが該当します。(※2)
これらを財務情報とあわせて説明することで、企業の未来の成長力を立体的に示すことが求められています。
ちなみに、SSBJ(サステナビリティ基準委員会) が策定を進めている日本版の開示基準では、「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標と目標(KPI)」の4要素を中心に、企業がサステナビリティ関連リスク・機会をどのように把握し、価値創造に結びつけているかを一貫して説明することが求められています。
※2:IIRC「統合報告フレームワーク」、経済産業省「価値協創ガイダンス」における無形資産の整理、および ISSB(IFRS サステナビリティ開示基準)・SSBJの開示方針に基づく。
Q3. 非財務情報開示は企業にとってどんな効果がある?
非財務情報の開示には、制度対応以上の意義があります。企業の強みや価値創造プロセスを明確に伝えることで、投資家には将来の成長性への期待や収益の源泉を示す材料となり、従業員には企業文化や人材の活躍・成長のあり方を知るための手がかりとなります。また、顧客や社会に対しては、企業の姿勢・信頼性・サステナビリティへの取り組みを可視化し、ブランド価値の向上や選ばれる理由の強化につながります。
つまり非財務情報開示は、企業が“未来の価値”を多面的に発信し、ステークホルダーとの関係を深めるための有効な手段なのです。
企業が直面する課題と対応の方向性
非財務情報の開示を進めるうえで、企業が抱える主な課題は次のとおりです。
● 情報の分散と整合性の欠如
環境・人的資本・ガバナンスなどのテーマが部署ごとに管理されており、データ形式や基準がバラバラ。社内で収集した情報を統合・整理し、外部発信に活かす仕組みづくりが必要です。
● 基準・保証対応の複雑化
ISSB・GRI・TCFDなど複数の国際的な基準に対応した開示物の制作や取捨選択や、第三者保証対応への準備が負担に。単独部署では限界があり、部門横断の連携体制が求められます。
● 経営とコミュニケーションの分断
IR、広報、サステナビリティ、経営企画などが別々に情報を扱うことで、メッセージの一貫性が担保しにくい。戦略・データ・表現を統合した「非財務情報戦略」の構築が急務です。
● 「語り(ナラティブ)」の設計が難しい
非財務情報は定量データだけでは伝わらず、企業の考え方や価値観をどう表現するかが重要。何を語るべきか、どんなトーンで伝えるかを設計できていないケースが多く見られます。
非財務情報開示の「つまずきポイント」
非財務情報開示は、制度対応や情報収集の重要性が理解されていても、実務の現場ではさまざまな“壁”に直面します。特に次のようなつまずきが、多くの企業で共通して見られます。
| つまずきポイント | 内容・具体例 |
|---|---|
| ① どこから手をつければいいかわからない | 非財務情報の範囲が広く、開示対象の優先順位や基準選定に迷う。環境・人的資本・ガバナンスなどテーマが多岐にわたり、整理段階でプロジェクトが停滞しがち。 |
| ② データはあるが、語れる形になっていない | 調査報告書・CSR資料・社内アンケートなど情報源は存在するが、“ストーリーとして再構成”できていない。結果、「何を大切にしている企業か」が伝わらない。 |
| ③ KPIとナラティブがつながらない | 数値指標(離職率、排出量、女性管理職比率など)は整備しても、経営戦略やブランド価値との関係を説明できない。報告が“データの羅列”で終わってしまう。 |
| ④ ステークホルダー視点が抜け落ちている | 開示目的が「制度対応」に偏り、投資家・社員・顧客など受け手の関心を踏まえたメッセージ設計になっていない。伝わらない・響かない開示に。 |
| ⑤ 経営層の“言葉”が弱い | 経営メッセージが抽象的で、“自社の未来を自分の言葉で語る”表現になっていない。統合報告書などでも、経営の想いとデータの整合が取れていない。 |
このように、非財務情報開示の課題は、単なる制度対応ではなく、「情報の設計」と「表現のデザイン」をいかに両立させるかにあります。
次章では、これらの課題を踏まえ、企業がより戦略的・魅力的に非財務情報を発信していくためのアプローチをご紹介します。
非財務情報開示を進めるための3つのアプローチ
非財務情報開示を実効性のあるものにするには、単なる制度対応ではなく、「経営のストーリーをどう設計し、どう伝えるか」を軸に据えることが大切です。
そのための基本的なアプローチは、次の3つに整理できます。
| アプローチ | 取り組み内容・ポイント |
|---|---|
| ① 戦略の言語化 | 自社のパーパスや中長期戦略と、サステナビリティ・人的資本など非財務領域をどう結びつけるかを明確にする。単なる“施策の列挙”ではなく、「どんな未来を描き、どう実現するのか」を語る構造を設計する。 |
| ②データの集約とナラティブに基づく可視 | 部署ごとに分散している情報を集約し、財務・非財務の両面から一貫したストーリーを作る。KPI(定量)とナラティブ(定性)を連動させ、経営判断と開示内容を結びつける。 |
| ③ 発信のデザイン | 投資家・社員・顧客など受け手に合わせて、「伝える内容・トーン・チャネル(媒体)」を最適化。報告書、ウェブサイト、動画、PRなどを組み合わせ、共感と信頼を生む“語り方”を設計する。 |
この3つのアプローチを循環的に回すことで、非財務情報は“制度対応としての報告”から、“企業価値を高める発信”へと進化します。
次章では、この考え方をベースに、支援している例として、電通が支援する「非財務情報開示」への実践アプローチについて紹介します。

電通が支援する「非財務情報開示」への実践アプローチ
非財務情報開示を「制度対応」ではなく「企業価値を高めるコミュニケーション」として位置づけるために、電通では、戦略設計からデータ分析、メッセージ開発、発信までを一気通貫で支援しています。ここでは、先に挙げた3つのアプローチに対応する形で、電通の具体的な支援例を紹介します。
| アプローチ | 電通の実践例・支援内容 |
|---|---|
| ① 戦略の言語化を支援する:非財務情報発信コンサルティング | サステナビリティ経営や人的資本経営に精通した専門チームが、現状分析と開示方針の策定を支援。経営戦略と社会的価値創出の関係を可視化し、「何を・誰に・どう伝えるか」を設計。サステナビリティ、PR、DXなど複数領域のプロフェッショナルが横断的に伴走。 |
| ② データを“語れる情報”へ転換する:非財務価値サーベイ | 財務・非財務データを統合分析し、企業価値に寄与する要素(イメージ因子・活動・資産)を抽出。経営層・関係部署とのセッションを通じて、どの活動を強調・強化すべきかを明確化。データに裏づけられた開示ストーリーを構築。 |
| ③ 発信のデザインを支援する:統合レポートリニューアル/メッセージ開発 | 有価証券報告書とのすみ分けを意識し、読まれる・理解される「新しい統合レポート」への刷新を支援。経営層の想いを“自身の言葉”で発信するメッセージ開発を行い、統合報告書やスピーチ原稿への落とし込みまで伴走。発信チャネル(サイト・動画・PR)も最適化。 |
これらの取り組みは、単に「報告書を作る」ことではなく、企業の未来をどう描き、それを社会にどう伝えるかという経営課題そのものへのアプローチです。
非財務情報の信頼性と共感性を両立させるために、電通は「データ×ナラティブ×デザイン」の統合支援で企業の変革を支えています。
まとめ──「制度対応」から「価値共創」へ
2027年の有価証券報告書への非財務情報開示義務化は、企業にとって単なる制度対応ではなく、自社の存在意義や未来の価値を社会と共有する転換点です。
今、求められているのは「何を報告するか」ではなく、「どのように伝え、共感を生むか」。財務と非財務の両面から、自社らしいストーリーで“価値を語る”姿勢が、ステークホルダーとの信頼を深め、企業ブランドを育てていきます。
もっとも、ここまで述べてきた非財務情報の開示そのものは、企業活動の“目的”ではありません。重要なのは――その取り組みを通じて企業価値をどう高めていくか。
「財務情報が示す「成果」と、非財務情報が示す「未来の可能性」。両者を統合し、自社の成長シナリオとして伝えていくことこそが、企業の情報発信戦略の本質です。
電通は、サステナビリティや人的資本経営の専門知見と、コミュニケーション領域で培った「人の心を動かすデザイン力」を掛け合わせ、企業の非財務情報を“伝わる価値”へと変換する総合支援を行っています。
制度対応の枠を超え、財務 × 非財務を統合した企業価値向上のための情報発信戦略を構築すること──そのパートナーとして企業の挑戦に寄り添っていきます。
企業価値を持続的に高めるための打ち手のひとつとして、非財務情報開示をどう位置づけ、どう活かすか。これこそが、これからの企業の情報発信戦略に求められる視点です。