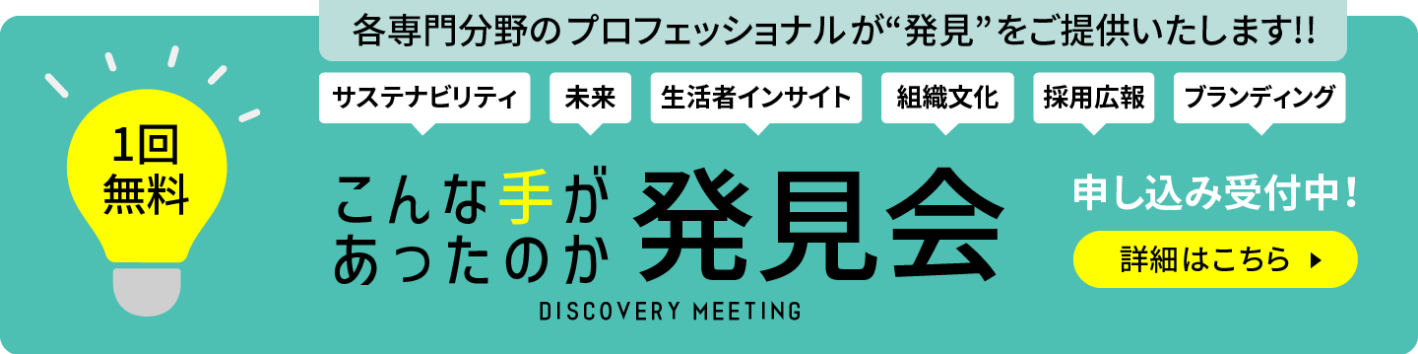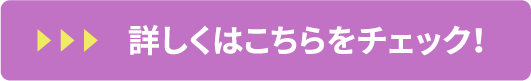商品開発は、企業の成長と競争力を維持するための重要なプロセスです。本記事では、消費者視点を重視したデータドリブンなアプローチから、ブランディングやオープンイノベーションまで、商品開発に必要なポイントを解説します。また、具体的な進め方や考え方・戦略、成功事例と失敗事例を通じて、実践的な知識を身につけることができます。革新を生み出すためのヒントを掴み、次の大ヒット商品を生み出す一助としてください。
INDEX
商品開発に必要なポイント
商品開発はマーケティング戦略と密接に結びついており、消費者のニーズを深く理解し、それに基づいた革新的な商品やサービスを提供することが重要です。今日的なアプローチのポイントは以下の6つが挙げられます。
消費者視点の重視
消費者の行動や心理を徹底的に分析し、その洞察を商品開発に活かすことは、商品開発に取り組むうえで最重要ポイントです。消費者の、商品やカテゴリーに対するニーズやウォンツ、消費のトレンドをまず把握します。その際には、耳を傾けるべき消費者が誰なのか、誰に向けての商品開発なのかを明確にしておく必要があります。マーケティングリサーチを通じて、消費者のニーズやトレンドを把握し、それに応じた商品を設計します。
データドリブンなアプローチ
商品開発の意思決定には、担当者の勘や過去の経験だけではなく、データに基づく判断が不可欠です。デジタル技術の進化により、ビッグデータを用いた市場の分析や、自由回答を解析して消費者の意識やニーズをあぶりだすツールなどが、以前より利用しやすくなっています。積極的に活用するとよいでしょう。
ブランディングとストーリーテリング
商品は、単なる物理的な存在ではなく、消費者の心の中にあるブランドの一部です。そのため、商品開発の段階から、商品の背後にあるストーリーやコンセプトを適切に設計し、消費者に感情的なつながりを提供するように考えておくことも必要です。
コラボレーションとオープンイノベーション
昨今では、異なる分野の専門家や企業との連携を通じて新しいアイデアや視点を取り入れることで、自社のリソースだけでは開発できない革新的な商品を創造する取り組みが活発に行われています。他社と自社のリソースを掛け合わせる「コラボレーション」や、自社に不足しがちなリソースを外部から取り入れて革新的な商品を外部と共創する「オープンイノベーション」と言った考え方を取り入れることも商品開発において大切なポイントになります。
サステナビリティの考慮
商品開発では、社会的課題を解決するというコンセプトも大切です。近年では、環境への配慮や社会的な責任が重視されています。商品開発においてもこうした持続可能性を考慮した材料選びや製造プロセスが求められています。
マーケティングとの統合
商品開発は、マーケティングのプロセスの一部です。シームレスに統合されることで、消費者に最適なタイミングで最適な価値を提供することが可能になります。市場投入のタイミングやプロモーション戦略なども商品開発を行う上で重要な要素となります。
商品開発の進め方

商品開発で成功するためには、顧客の深層的な欲望や市場トレンドを理解することが不可欠です。欲望を基点とした商品は顧客の心を動かし、高い顧客ロイヤルティを生むため、アイデア出しやコンセプト設計の段階で欲望を捉え理解することが重要です。また、フィードバック情報は非常に重要ですが、企業のブランドイメージを損なうような戦略を採用するのは逆効果です。つまり、企業のブランドと経営戦略に合った形で商品開発を進めることが大切です。要するに、顧客の意見を反映させつつも、自社のブランドを大切にし、一貫した方向性で商品を作ることが求められます。
ステップ1.アイデア出し
商品開発の最初の段階はアイデア出しです。市場調査に基づきなから、顧客が求めているものや、未充足のニーズ・ウォンツを満たすことなど、市場のトレンドを踏まえたアイデアを出し合います。この際、すでに顕在化している消費者のニーズやウォンツを把握するだけでなく、その背後に潜む消費者の「欲望」まで掘り下げて深い洞察を得ておくと、良いアイデアを生み出す可能性が高まります。アイデアを出す前に、こうしたプロセスを組み込んでおくことは、商品開発を成功させる近道となります。また、アイデア出しの際には、発想を制限しないように、商品開発チーム内での批判は抑えるなどの取り組みも大切です。
ステップ2.コンセプト設計
ターゲット市場や顧客が求めているものを明確にし、商品がどのような価値を提供するかを定義します。競合商品との差別化も考慮します。開発チームが、認識のブレがなく商品コンセプトを共有するために、簡単なスケッチやラフデザインの活用が効果的です。最近では、3Dモデリングソフトを利用して商品コンセプトを作り上げるケースも増えてきています。3Dで立体的に新商品を観察・評価できるので、開発チーム内での理解は進みます。また、この段階で消費者にコンセプトテストを行ってニーズの有無を確認する場合にも効果的です。
ステップ3.プロトタイプ作成
新商品のプロトタイプを作成し、実際に触れてみることで機能やデザインを確認します。より多くの視点で商品の改善点を見つけるためにも、開発チームだけでなく、外部の人間からのフィードバックを得ることも大切です。外部の人間には、「アイデア出し」でセグメントをした顧客層を抜擢すると効果的です。プロトタイプに完成度を求めるあまり、試作品が遅れることがないようにしましょう。このフェーズではフィードバックによる改善が重要になります。改善と試作のサイクルを速めることで、完成度は上がっていきます。
ステップ4.検証とテスト
フィードバックに基づいてブラッシュアップされたプロトタイプを基に、実際に販売される商品を作成し、検証とテストを行います。検証は、商品がプロトタイプ作成で得たフィードバックを的確に反映しているかを確認するプロセスです。想定する顧客や市場にしっかりとフィットするのかも併せて確認します。テストは製品が仕様どおり機能するかを確認するプロセスです。また、安全性や規制対応といった評価項目が設定されることもあります。
ステップ5.商品化準備
商品化準備では量産体制整備、流通計画の策定、マーケティングの3本柱を同時に進めていきます。このフェーズでは、他部署との調整が重要です。調整が遅れた場合は、商品販売が大きく遅れるリスクが発生します。生産ラインの増設やカスタマイズ、サプライチェーン構築は既存リソースとの調整もあるため、自社で主導性を持って進めなければなりません。一方で、マーケティングは外部に委託する選択肢もあります。
ステップ6.市場投入とフィードバック
商品を量産化し、流通させ、実際に店頭で発売します。マーケティング施策が成功していれば、発売前から商品は広く認知され、当初からの高い売上が期待できるでしょう。しかし、商品開発は発売がゴールではありません。逐次、ターゲット客や購入者からのフィードバックを収集し、改善点を取り入れていくことが大切です。狙い通りのポジションを取れる企画になっているか、想定したターゲットに受け入れられているか、商品自体に思わぬ課題が生じていないかなど、顧客・商品・企画の課題を点検するとよいでしょう。
近年は、SNSなどで良い評価でも悪い評価でも、広く拡散されやすい傾向がありますので、フィードバックには適切に対応することが大切です。商品がブランド毀損を招くといった事態を招かぬよう、しっかりと取り組みましょう。
ちなみに、電通グループではECを通じて上市を行う際に必要な作業の支援サービスや、SNSを用いた販売促進を行う際のソリューションサービスなどを提供していますので、ご興味のある方は下記の記事もご覧ください。
⇒UGC(User Generated Contents)を活用してECを向上させる「ULVA」
商品開発の考え方・戦略

ここでは商品開発の戦略として市場アプローチ型、顧客/市場主導型、技術主導型、既存リソース活用型の4つを解説します。企業の方針や市場でのポジションを総合的に考慮して、適切な戦略を採用することが大切です。
また、企業はいくつかの戦略を組み合わせて商品開発を進めるケースもあります。例えば、後述の「商品開発の成功事例」で紹介する「iPhone」は、市場アプローチ型戦略と技術主導型戦略を組み合わせた商品開発事例といえます。
関連記事:新規事業立ち上げを成功させる8つのプロセス!進め方や事例についても紹介
市場アプローチ型戦略
市場アプローチ型戦略は、企業側が主導性を持って新規市場にアプローチし、新商品を投入する戦略です。特に海外市場進出や多角化戦略などで、経済成長を目指す企業にとって有効です。
企業主導であることから、商品開発は比較的自由かつスムーズに進みます。一方で、市場進出に専念するあまり、顧客が企業の新しい試みを受け入れてくれるかどうか、顧客が求めているものをないがしろにしてしまわないか、注意が必要です。
顧客/市場主導型戦略
顧客/市場主導型戦略は市場アプローチ型戦略と対照的に、顧客の声や市場動向を重視して商品を開発していきます。既存顧客基盤を強化したい企業や、競争の激しい市場での差別化を目指す企業に適した戦略です。一方で、顧客が求めるものは常に変化していきます。商品の売上を継続させるためには、商品改良やプロモーションが欠かせないため、思わぬコストがかさむ可能性があります。
技術主導型戦略
新技術を活かして新商品の開発を進める戦略です。技術力を強みとする企業、特にハイテク産業や研究開発を積極的に行う企業に適した戦略といえます。他にない商品を開発できる可能性がある一方で、プロトタイプの作成や検証・テストといった商品化前のプロセスでコストが大きくなることもあります。商品開発に成功した場合は、市場シェアの拡大や企業ブランディングに大きな貢献を果たします。
既存リソース活用型戦略
既存の生産ラインやリソースを活用し、効率的かつスピーディーに新商品を開発する戦略です。商品開発コストを抑えつつ、新たな顧客獲得を狙う企業にとって的確な戦略といえます。この戦略で開発される商品の種類としては、商品ラインナップを拡充するシリーズ商品が挙げられます。また、他業種とのコラボレーションといった進め方もあります。比較的低リスクで商品を開発できますが、革新性に欠ける可能性があります。
商品開発の成功事例
前章の商品開発の考え方・戦略で解説した各種戦略をうまく組み合わせることで、商品開発を成功させた事例を紹介します。

Apple - iPhone
Appleが2007年に発売した「iPhone」は、市場アプローチ型戦略と技術主導型戦略を組み合わせた商品開発の成功事例です。タッチスクリーンやフリック入力といったユーザビリティーは市場に衝撃を与えました。また、電話やメール、カメラ、音楽プレーヤー、インターネット機能を1つに統合したiOSプラットフォームによって、携帯電話を新たなフェーズに進化させたといえます。
Allbirds - サステナブルシューズ
Allbirdsは米国のシューズメーカーです。サステナブルなシューズの新商品開発を成功させました。コンセプト設計の段階で、市場のエコ意識の高まりをしっかりと把握したことが成功要因といえます。ウール、樹木繊維、サトウキビなど、天然素材をシューズ材料に採用したことで、エコ意識の高い顧客からの支持を獲得しました。
Beyond Meat - 植物性代替肉
Beyond Meatは植物ベースの肉代替品を製造する企業で、従来の肉の風味や食感を模倣した製品を提供しています。顧客が求める「健康的で持続可能な食生活」に応えるため、植物性代替肉を開発しました。動物肉を避ける消費者が増加傾向にあることに注目して、商品開発を進めたことが成功要因といえます。
Beyond Meatは植物性代替肉として日本でも知られるようになっています。Microsoft創業者のビル・ゲイツ氏や米国の人気俳優レオナルド・ディカプリオ氏もBeyond Meatの取り組みに賛同し、出資をしていることでも有名です。
Dyson - サイクロン・コードレス掃除機
Dysonは従来の掃除機の「吸引力が弱まる」といった課題に注目しました。そして自社独自の「サイクロン技術」を用いて商品開発を成功させました。掃除機をコードレスにしてユーザビリティーを高めたことも主要な成功要因の1つです。
特に、Dysonはプロトタイプ作成と検証とテストに力を入れました。試作したプロトタイプは5,000以上に上ります。「プロトタイプ作成」の段階でテストを繰り返し、使いやすさと機能性を徹底的に追求しました。
Oatly - オーツミルク
Oatlyはオーツ麦を主成分とした植物ベースの乳製品代替品を提供するスウェーデンの企業です。植物(オート麦)由来のミルク「オーツミルク」の商品開発に成功しました。Oatlyは当初、乳糖不耐症患者の課題を解決するために商品開発を始めています。しかしその後、オーツミルクはヴィーガンやエコ意識の高い顧客からも支持を受け、世界中で流通するようになります。
商品開発の失敗事例
商品開発は顧客の求めているもの、市場のトレンドを見誤ることで失敗します。また、マーケティングの要因も小さくありません。
Amazon - Fire Phone
Amazon Fire Phoneは、2014年にAmazonがスマートフォン市場に参入するために開発した端末です。3D表示機能や商品スキャン機能(Firefly)を搭載し、Amazonの独自OS(Fire OS)を使用していました。しかし、発売後すぐに販売不振に陥ります。
主な失敗要因は、顧客が求めるものの誤認です。ユーザーが望んでいない機能の導入、基本的なアプリケーション不足は多くの不評を集めました。
Coka Cola - New Coke
1985年、Coca-Colaは競合するPepsiの台頭に対抗するため、「New Coke」を開発しました。New Cokeは従来のCoca-Colaのレシピを改良し、甘さを増したものでした。しかし、わずか3カ月程度で販売を終了しています。
主な失敗要因は、顧客が抱く商品への感情的な愛着を過小評価したことです。プロトタイプ作成の段階では、想定顧客層からのフィードバックは好評でした。しかし、フィードバック調査の対象となった消費者は、従来のCokeがなくなってしまうことを知らされていなかったことから、上市後に強い反発を招いてしまいました。ブランドのリニューアルで新たな商品を開発・投入する場合は特に、それまでに獲得したブランドに対する顧客ロイヤルティに充分注意を払ってフィードバックを設計・実施する必要があります。
Microsoft - Zune
Microsoft Zuneは、Microsoftが2006年11月に発売した携帯音楽プレーヤーです。Zuneは無線同期機能や定額音楽サービス「Zune Pass」などを提供しましたが、市場での人気を獲得するには至らず、2011年に生産が終了しました。
主な失敗要因は、市場参入が後発であったにもかかわらず、充分な差別化点を消費者が認識しなかったという点です。発売当時、iPodがすでに市場を支配していたため、Zuneには消費者をスイッチさせるだけの明確な差別化ポイントを認識させる必要がありました。
まとめ~商品開発成功のカギは顧客の欲望を捉えること~

商品開発で成功するためには、顧客の深層的な欲望や市場トレンドを理解することが不可欠です。欲望を基点とした商品は顧客の心を動かし、高い顧客ロイヤルティを生むため、アイデア出しやコンセプト設計の段階で欲望を捉え理解することが重要です。また、顧客からのフィードバック情報は非常に重要ですが、全ての意見をそのまま受け入れるのではなく、企業のブランドと経営戦略に合った形で意見を取り入れながら商品開発を進めることが大切です。つまり、顧客の意見を反映させつつも、自社のブランドを大切にし、一貫した方向性で商品を作ることが求められます。
電通は、顧客の深層的な欲望を基点とした商品開発やマーケティング施策を支援するプログラム「DENTSU DESIRE DESIGN(デンツウ・デザイア・デザイン)」で、真に顧客が求める商品を追求する商品開発支援を行っています。
企業の強みをしっかりと活かし、アイデア出しから市場投入、マーケティングまで的確なソリューションで商品開発の伴走支援をいたしますので、ご興味のある方はぜひ、下記にお気軽にご相談ください。
PROFILE