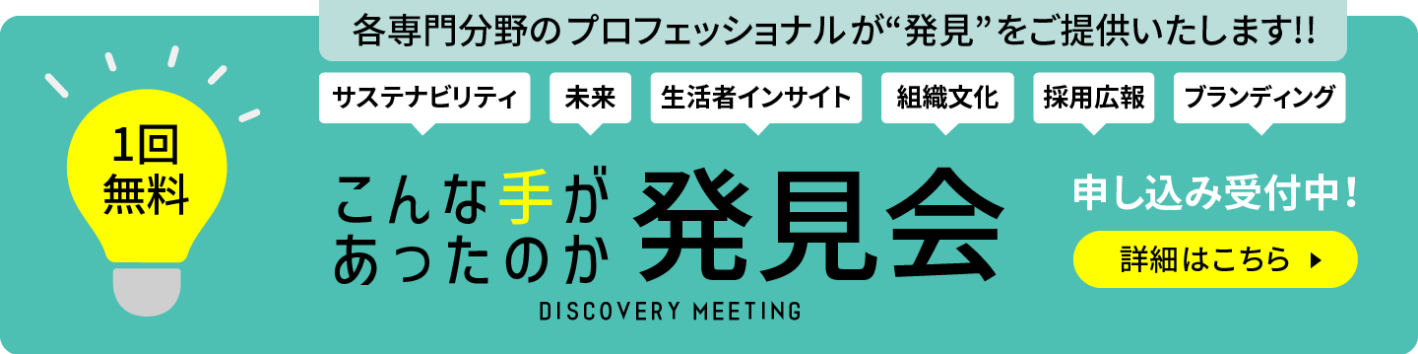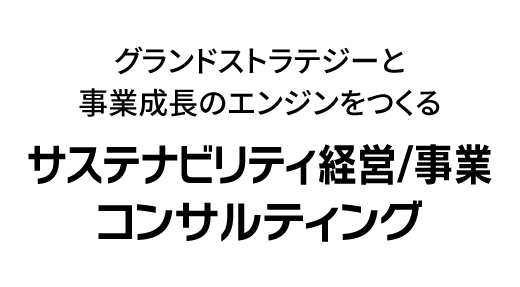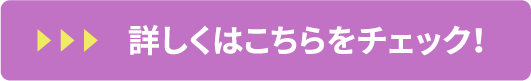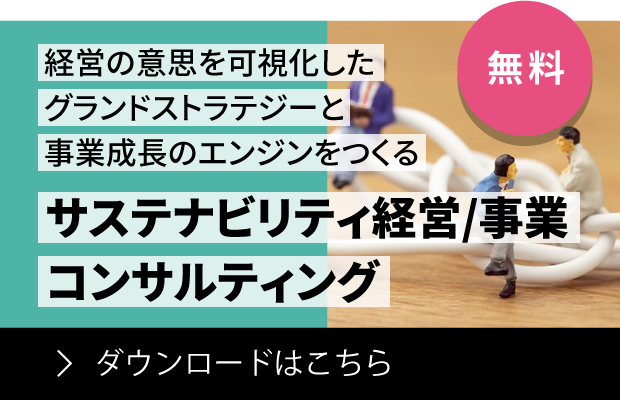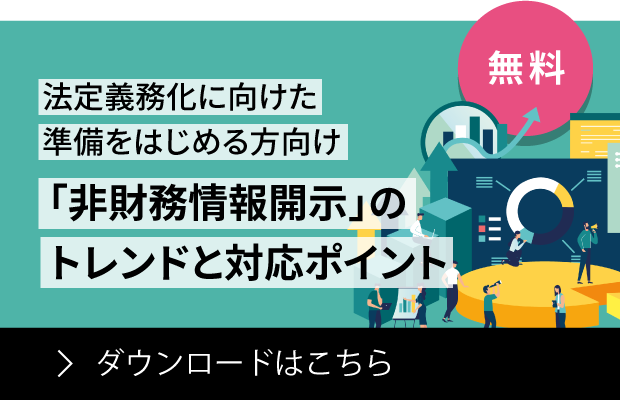「サステナビリティ経営」や「人的資本経営」「ウェルビーイング」など、経営に新たな概念が生まれている昨今。時代に即し、リードする企業であるために、経営に求められるものとは何なのでしょうか。ESGを通じた企業変革を研究してきた慶應義塾大学 保田隆明教授と、企業の経営を伴走支援する電通サステナビリティコンサルティング室の小野・福島が、語り合いました。
PROFILE
INDEX
経営戦略と人事戦略の分断が、大きな課題に
福島:私は電通でクリエイティブプランナーという職種で働いていますが、ここ数年は広告表現だけではなく、企業経営や事業戦略のご相談をいただくケースが増えてきました。研究者であり、上場企業の社外取締役経験も豊富な保田先生にはいつもお世話になっております。
小野:ありがとうございます。おかげさまで経営者伴走の実績も増え、最近では「サステナビリティ経営/事業 コンサルティング」というソリューションもリリースしました。
保田:いろんな企業の経営を支援していく中で、最近課題に感じていることはありますか?
小野:そうですね、経営者の皆さんと話していると、経営変革の話が出ても、人事戦略と連動したお話をうかがうことはあまり多くなく、そこに課題があると思っています。日本の産業界では、経営戦略と人事戦略を無意識に切り離して考えてしまっているような気がしていて。
福島:リスキリングなど人事戦略を強化しているはずなのに、なかなか経営戦略に結びついて見えないケースは確かに多いですね。
小野:多くの企業で行われているリスキリングは、研修や再教育のプラットフォームを用意して、そこから自分に関連するプログラムを選んで勉強してくださいというスタイルが多い。でも、これで投資した見返りがちゃんと得られるかどうか・・・
保田:たとえが適切かわかりませんが、かつての経営は「体操の人は体操で、野球の人は野球でメダルをとってください」という考え方がほとんどでした。その中で「プレイする競技自体を変えていきましょう」という人事戦略を打ち出しても、まだ組織は野球と体操に分かれてしまっている。だからいくらリスキリングを推奨しても、実態は「野球なら変化球、体操なら新しい技を覚える」にとどまり、競技の枠から出られていないのでしょう。

必要なのは、mustよりもwill/can発想
小野:そもそも体操していた人に野球の能力を磨けと言っても、「なぜ自分がそれをやるのか」っていうマインドがないと、スキルを獲得してもパフォーマンスが上がらないですよね。リスキリングをするマインド醸成のために最近では全社ビジョンを打ち立てる企業も増えていますが、それだけでは従業員目線の動機付けとして弱いとも感じています。よくパーパスやビジョンを浸透させてほしいと言われますが、言葉だけ浸透させてもダメなんじゃないかと。
保田:その課題は、will/can/mustの視点から考えてみると分かりやすいかもしれません。ミッションやビジョンを再策定し、頑張って社内に浸透させたところで、結局従業員にとってはmustへのアプローチがちょっと変わるぐらいで終わってしまいます。mustしかしてない人にいくらリスキリングしても、mustしかできないですから。
福島:willやcanができるようになる人事戦略が必要、ということですね。
保田:そうですね。そもそも経営層がwill/can発想を持つ必要があると思います。私が参加してきた役員会の多くも、本当にmustの話ばっかりなのです。月次業績を見て、ここを改善しなくちゃいけないとか、とにかくやらなくちゃいけないことだらけ。でも、そればっかりやっていると頭のCPUが全部そっちに取られちゃうので、「次にどうすればこの会社は面白くなるんだろう?エキサイティングな仕事が生まれるんだろう?」と考える余裕が残ってないんですよね。
小野:もしかしたらその点については、電通の「サステナビリティ経営/事業 コンサルティング」がご支援できるポイントかもしれません。というのも、メンバーは私のような戦略クリエイティブディレクターやプランナーなので、「どうすれば面白くできるか?」というwill/can発想がわりと染みついているから。こういう立場の人間が経営層と直接対話することで、発想転換のきっかけが生み出せたらとは常に考えています。

保田:一般的なコンサルティングファームだと、mustの部分、「やらなくちゃいけないことをどう効率化するか」という支援が中心だと思うので、電通さんがやられているご支援はそれらと全く性質が違いますよね。
小野:クライアントの取締役会に参加させていただくと、役員の方が、全員に対してではなく僕に向かって「小野さん、私こう思うんですよね」と話されることがあります。利害関係があるから役員同士では面と向かって言いにくいことも、外部の人間だからこそ話せるのかもしれません。
保田:経営者は会議の場で意思決定するだけでなく、そうやって自分の考えを利害関係抜きに吐き出しながら、本質的な戦略思考をする時間が必要だと思いますね。海外の経営者だと意識的にクワイエットタイム(※)を設けたりしていますが、いきなりそんな習慣をつくるのは難しいでしょう。その代わりに、経営層がクリエイティブ系の人に相談できるような、今までと違う環境を作るのは良いと思います。しかも思考がぶっとびすぎていない、サステナビリティや経営用語もわかって、社員にもわかりやすく説明してくれるクリエイティブディレクターが伴走してくれるなら、客観的で本質的な意思決定ができそうですし、実行支援も心強いと思います。
※クワイエットタイム…他者とのやりとり・会話を遮断し集中して業務に取り組むための時間
クリエイティブディレクターの視点を、非連続イノベーションのヒントに
福島:保田先生は、具体的にどの経営領域にクリエイティブディレクターが伴走すると、インパクトにつながると思いますか。
保田:経営のビジョン設計ではないでしょうか。日本のプライム上場企業の8割以上が中期経営計画を立てていますが、正直、真面目一辺倒で味気のないものになっています。ワクワクが完全に足りないんです。実は中計って海外ではほとんど作っていなくて、それは3~5年のスパンで数字を公表したところで結局計画と見合わなくなるから。それよりも、もっとロングスパンで「10年後はこんな未来になるから、こんな方向に行きたい」というビジョンの方が必要とされています。2050年にワクワクする世界があって、その中で自分たちの会社はどうなっているか。そのビジョン設計のところにクリエイティブディレクターの伴走価値があると思います。そもそもPBR(株価純資産倍率)は未来への期待値ですから。
小野:確かに投資家からすれば、今までの延長線ではないビジョンや新しいイノベーションについて知りたいはずですよね。
保田:直近の興味深い例では、ウォルマートのPBRが30倍になっています。数年前まではアマゾンに駆逐されてしまうかもしれないと思われていた企業が、DXで業績を改善し、テックカンパニーと同レベルで株式市場から評価されるまでに回復している。こうしたイノベーションが起こるとき、その種は現場にあることも多いんです。それを経営陣が新しい発想ですくい上げられるかどうか。そうした動きがないと、PBRが2桁超えるようなことはありません。
福島:なるほど、そこで経営戦略と人材戦略がつながりますね。人材戦略でwill/can視点を持った従業員を増やし、経営陣もまた新たな発想でそれを汲み取っていけば、次の経営戦略が拓ける。
保田:その通りです。投資家もそれが見たいから、人的資本経営に注目しているんです。例えば半導体を強みとする企業がmust発想でイノベーションを考えても、今の半導体の延長線上にあるプロダクトアウトの事業しか思いつかないことが多い。でも本当に期待されているのは、「これまで思いつかなかったこんなところでも半導体技術が使えた!」という非連続の発想です。
福島:結局、変革を起こすのも、業績を高めるのも「人」。経営層と向き合いながら、その先にいる従業員や投資家、お客様というマルチステークホルダーをつないで、一緒に動かしていく仕組みづくりがカギになりそうですね。

「ウェルビーイング」とサステナビリティ経営の関係とは?
福島:ところで人的資本経営といえば、最近は「ウェルビーイング」が大きな注目を集めています。サステナビリティ経営とも切っても切れない概念かと思うのですが、保田先生は経営においてこの言葉をどう捉えていますか?
保田:おっしゃる通り、「ウェルビーイング」は今の経営の注目テーマの1つですね。古くて新しい「健康経営」も再び注目されています。つい最近までは、従業員エンゲージメントが高くなれば生産性が高まって業績も上がるというわかりやすさから「エンゲージメント指標」がよく使われていましたが、従業員からすればなんだかお仕着せ感がある言葉。それに対してウェルビーイングは、従業員の目線に立つ言葉ですね。
福島:ただウェルビーイングって、社員が千人いたら千通りのウェルビーイングの定義があるわけですから、経営者側からすると「それどうやって測る? 何をもってよしとする?」という課題が生じませんか? 指標づくりが難しそうです。
小野:ウェルビーイングを何のためにやるかという目的も企業によって全然違うし、経営からすると「そんなことより目の前の数字が上がる方が大事だ」とも思われそうですよね。
保田:そうですね、経営はもちろん数字重視。人的資本経営もウェルビーイングも「なんでそれをやるんだっけ?」を考えると、答えは業績か株価を上げるためです。これを全部オブラートに包んでやってきたのが、人的資本経営1.0だった。でも今はステージが進んで、投資家からも「オブラートに包むのはやめよう、業績や株価との結びつきをちゃんとつくろうよ」という動きが出てきています。
福島:ウェルビーイングそのものの指標にこだわるのではなく、業績や株価にどう結びつくかを考えよう、ということでしょうか。
保田:業績は、アウトプット(事業活動の結果)であってアウトカム(最終成果、社会的な影響)ではありません。ただ、アウトプットで業績が出れば、社会的インパクトのアウトカムにつながる。今日の話のキーワードとして出てきた「人的資本経営」「ウェルビーイング」は、サステナビリティ経営のインプットとアウトカムをつなぐ、注目要素として捉えるとよいでしょう。商品のライフサイクルが短くなっている中で、今のスキルが使えるのはもって3年から5年。かといって5年後にその人たちをリプレイスできるわけではなく、企業活動は続いていく。そのとき、従業員がのびのび自由な発想で仕事ができるようになっていれば、新サービスも新規事業も展開していけるはず。ウェルビーイングは、そうした長期経営思想だと捉えています。

人材戦略も見据えた、サステナビリティ経営の伴走支援
保田:経営支援においてもまた、mustを超えたwill/can視点がますます求められていると思います。人的資本経営もサステナビリティ経営も、現場的にはお仕着せ感ややらされ感がある中、どうしても優等生的に繕うという姿勢になりがちです。しかし、それでは真に機能するように思えません。体裁よりも、機能するかどうかがより重要ですから、現場を「ノせる」必要があります。組織も人も、頭では重要性は分かっていても楽しくなければ動いてくれません。あ、この取り組み、創造的だな、クリエイティブだな、みたいなエッセンスがあれば現場はとても喜んで取り組んでくれる気がします。そこでまさに、今後の電通さんの支援ソリューションに期待しています。
小野:ロジカルに考えていくだけでは、当たり前の答えに行き着いてしまう。その思考の檻から抜け出すことは、なかなか自社内の対話だけでは難しい、という声を本当に多くの経営の皆様から伺います。僕たちの持つ、クリエイティブ発想は、解決策を考えることのみならず、より良い未来を目指すための探索のフェーズでも有効だと信じていますので、お気軽にお声掛け頂きたいです。
福島:経営層の皆様がワクワクする未来のビジョンを掲げるために。その言語化・可視化・物語化のお手伝いこそ、電通のクリエイティブディレクターが担える部分かもしれません。未来視点にたったビジョン設計、さらにはその景色を、従業員をはじめ多様なステークホルダーの皆様と共有するためのストーリー構築まで、ぜひご相談いただきたいです。