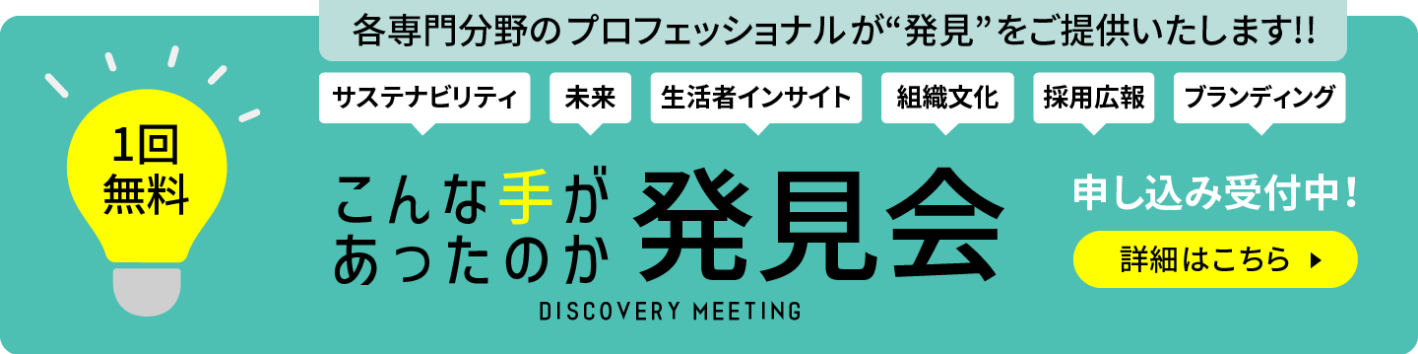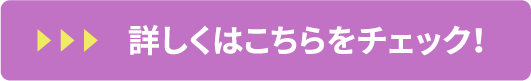暮らしが日ごとに便利になり、未来への希望にあふれていた昭和時代。それから数十年、先行き不透明な時代を迎えた今、「従来型のビジネスモデルでは成長が難しい」「合理化・効率化だけでは新たな価値を生み出せない」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。
こうした中、国内電通グループの横断組織「未来事業創研」が提案するのが、「未来」を軸にして企業価値を創出するアプローチです。つくりたい未来=ビジョンを明確にし、バックキャストでビジネスを考える。その基本思想から、事業構想プロセス、構想事例などを一冊にまとめた書籍『未来思考コンセプト―ポストSDGsのビジョンを描く』が2025年6月27日に発売されました。
なぜ今、「未来」がビジネスツールになり得るのか。電通 未来事業創研ファウンダーの吉田健太郎に、編集部が取材しました。
⇒未来事業創研の書籍『未来思考コンセプト―ポストSDGsのビジョンを描く』のご紹介ページはこちら
PROFILE
INDEX
2030年代は“量から質へ”の転換期
「未来事業創研」は、クライアント企業へのワークセッションやコンサルティングを通して、各社が抱えるビジネス課題の解決に取り組んでこられたかと思いますが、この度、書籍『未来思考コンセプト―ポストSDGsのビジョンを描く』を執筆した経緯を教えてください。
今、多くの企業が「未来」について悩みを抱えています。未来事業創研では未来に関するツールを定期的にアップデートしていますが、問い合わせがとても多く、ニーズの高さを感じていました。そこで、皆さんのビジネスに役立てていただくため、私たちのメソッドやフレームを紹介するこの書籍を執筆することにしたのです。
この2025年6月というタイミングで出版することも重要でした。2025年10月に大阪・関西万博が終わると、社会は一斉に2030年に向けて動き出します。2030年にはSDGsがゴールイヤーを迎えるわけですが、その時、「この先の未来、どうしよう」と悩む企業はますます増えるはず。2025年の今こそ、「未来」をビジネスツールとして活用いただきたいと思いました。
ひと口に「未来」と言っても、その射程はいろいろありますよね。どれくらい先をイメージすればいいのでしょうか。
私たちは、「2040年」を1つのターゲットにしています。日本では少子高齢化による「2040年問題」が控えていますし、3年後、5年後の近い未来をターゲットにしてしまうと、現状の延長線上でしかビジネスを考えられません。まずは2040年の未来を構想し、実現のためにどんな変化を2030年代に起こしていくのか、3年後、5年後の近い未来に何をすべきかを考えるためにも、2040年にスコープを置いています。
書籍のサブタイトルに「ポストSDGs」とありますが、2030年以降、社会やビジネスにどのような変化が起きるのでしょうか。
簡単に言えば、「量から質への転換」です。これまで世界は、大量生産・大量消費によりGDPを競い合っていましたが、人口減少が進む日本ではそのやり方はもう通用しません。にもかかわらず、多くの日本企業では前年比成長を目指し、とにかく前年よりも多くの量を売ろうとしている。そこに問題点があると思うのです。
企業成長に必要なことは、量的成長を求めるのではなく、利益を増やすことです。そのためには、より多くの対価が得られる価値を提供しなければなりません。どんな人が、どんな状況であれば価値を感じてもらえるのか。その点を丁寧に考え、「この価値にだったら対価を払う」と納得してもらえる特別な価値を創出し、価値を認識してくれる人に届けなければ、量から質へシフトできません。つまり、一人ひとりが幸せを感じる価値を提供すれば、その対価を得られる時代に変わっていくと思います。
そういった新たな価値を提供するために、未来を考えることが重要なんですね。
そうですね。企業の存続のためには、当面は従来型の量的成長も続けなければなりません。それとは別軸で、利益を生む新しい事業を考えましょう、そのために未来を「ビジネスツール」として使いましょう、というのが私たちの考え方です。そして、その新しい価値を創出するための指針が「未来コンセプト」です。
「未来コンセプト」とは、「つくりたい未来像」を描き、その未来を実現する新しい価値の創出に向けて、必要な事業や活動をどのように進めていくかという指針を言語化したものです。「未来コンセプト」を共有することで周囲を巻き込みやすくなりますし、迷った時の判断軸にもなります。さらには、存在意義も明確になりアイデンティティの創出にもつながります。そういった観点からも「未来」は魅力的で実用的な「ビジネスツール」だと考えています。このあたりの詳しい説明は、ぜひ書籍でご確認ください。

つくりたい未来像からバックキャストでビジネスを考える
今、「未来がビジネスツールになる」というお話がありましたが、未来を起点にビジネスを考えることがなぜ重要なのか、ポイントを教えてください。
ポイントは3つあります。1つ目は、これからの時代、生活者と社会が望む理想像を見据え、あるべき未来から逆算して何をすべきか考えることが必要だからです。今の世の中には、デジタルテクノロジーの発達により、生活者が欲するものが行き渡っていますよね。しかも、サービスによっては提供者が意図していない使われ方も広まっています。例えばInstagramは、きれいな写真をアップして「インスタ映え」を狙うSNSでしたが、今では情報共有やDM(ダイレクトメッセージ)のやりとりをするコミュニケーションツールになりました。要は、生活者サイドが「これってこういう使い方の方が良い」と自分たちにとって便利な使い方を広めていったわけです。企業はもっと生活者の視点に立ち、生活者が望むあるべき状態を考えることが必要だと思います。
さらに、社会が望む状態も考えなければなりません。環境問題を踏まえ、今では買い物にはエコバッグを持っていくのが一般的になりました。このようなあるべき状態は社会が求める状態でもあります。企業が「こういうものがいいんじゃないか」と押し付けるのではなく、生活者と社会が望むことを理想とし、そのために何をすべきかを考えていかねばならないと思います。
2つ目は、「当たり前」は簡単に変わるからです。エコバッグもそうですが、動画配信サービスの普及によってレンタルビデオ店に行く人が減ったり、キャッシュレスサービスによって現金が使われなくなったりと、当たり前だと思っていたことは時代によってどんどん変わっていきます。となれば、今の当たり前も長く続かないはず。だからこそ、未来を考える必要があるんです。
3つ目は、今の生活には「実は理不尽なこと」がたくさんあるからです。私自身が「そもそも論」派ということもあるのですが、例えば、毎日生活に欠かせないサービスを使っていて何かトラブルが起きて、すぐに対応してほしいとなったらコールセンターに電話しますよね。でも、電話の受付時間は限られていますし、メールで問い合わせだとすぐに返事がもらえない、AIチャットでもらちが明かない。企業側の理屈を考えれば仕方がないことですが、ユーザーは不便を強いられています。そんな現状を「そもそも世の中ってどうあるべきなんだっけ?」と考えるところからも、ビジネスチャンスは生まれると思います。
つまり、①生活者と社会が望む未来を理想とすべき、②「当たり前」は簡単に変わる、③そもそも今の当たり前には理不尽なことがたくさんある、というわけです。そのため、未来や理想像を設定し、そこから逆算してビジネスを考える必要があると思っています。
「未来を考える」というと、新規事業開発や先進技術を扱うような一部の部署の役割のように思っていました。でも、どんなビジネスパーソンにとっても他人事ではないんですね。未来思考でビジネスを考える上で、未来事業創研が提唱する「未来コンセプト」はどういった役割を果たすのでしょうか。
「未来コンセプト」は、先ほどお伝えした通り、自社が次に進むべき道筋です。多くの企業は売上やカテゴリーシェアをゴールに設定していますが、先ほども申し上げた通り、今後は量的成長を遂げることが難しくなっていきます。そんな中、別軸のゴールを設定するには、「こんな未来にしたい」という新しいビジョンを考える必要があります。未来をどうしたいかというコンセプトがはっきりすれば、やるべきことも見えてくる。現在の事業に加え、別の武器を手に入れたい企業にとっては、有効なアプローチだと思います。

業界の常識にとらわれない、自由な発想を生み出すには
未来事業創研では、未来を可視化し、未来に向けた価値創造の実現をサポートする「Future Craft Process」を提供していますよね。このプログラムは、本書で紹介されている「未来コンセプト」を導出するプロセスとどのような関係にあるのでしょうか。
事業会社は、食品会社なら食品業界、通信会社なら通信業界と、同じ業界のミクロな視点でビジネスを考えます。例えばコンビニでの販売量が多い飲料メーカーなら、コンビニに置いてもらえるかどうかという視点で新商品を考えますよね。でも、それでは新しい発想がなかなか生まれません。10年後は、飲料を通販の定期便で購入するのが一般的になっているかもしれませんし、ペットボトルで提供されていないかもしれません。さらには、既存のジャンルに縛られない飲料が出てくるかもしれませんし、そもそも水分の取り方が変わっている可能性があります。ミクロな視点にとらわれず、10年先、20年先の未来をマクロに妄想できなければ、新しい発想はアウトプットできないと思います。
そこで、マクロな視点で企業が「つくりたい未来像」を描き、その価値を明確にするためにできたプログラムが「Future Craft Process」です。「未来コンセプト」の導出プロセスでも、このプログラムと同じ考え方でつくりたい未来を描いていきます。プログラムの途中では、つくりたい未来像をアウトプットし、実現のために必要な商品・サービスのアイデアを出すのですが、その段階で直近のアイデアが生まれ、新商品の開発に結び付くケースもあります。今までのやり方ではなかなか新しい発想が生まれない、いつも同じような発想になってしまうというクライアント企業には、高く評価していただいています。
「未来コンセプト」の導出プロセスの詳細は書籍で詳しく紹介しておりますので、ぜひ書籍をご確認ください。
⇒未来事業創研の書籍『未来思考コンセプト―ポストSDGsのビジョンを描く』のご紹介ページはこちら
書籍『未来思考コンセプト―ポストSDGsのビジョンを描く』では、SF小説のような未来のビジネス構想も語られていました。とても面白かったのですが、現実から離れた未来を思い描くのは、なかなか難しいのでは……。
おっしゃる通り、社内で新しい発想をしようとしても難しいと思います。だからこそ未来事業創研の存在価値があるのです。例えば、企業内で「こんな未来が面白そう」「こんなことができたらいいな」と夢のような未来を語っても、「いや、無理でしょ」と否定されてしまうでしょう。ですが、私たちは「それはいいですね!」「こういう角度からなら実現できるかもしれません」と話を進めます。みなさんのクリエイティビティを、私たちが底上げしたり、引っ張り出したりして、具体的な未来像に落とし込んでいく。未来事業創研との共創セッションによって、ワクワクする「つくりたい未来像」が生まれていくのが特徴です。
そのためのツールも取りそろえています。未来の仮説探索を行う「未来曼荼羅」、100のテーマを掛け合わせて未来社会を考える「未来ファインダー100」、未来の生活者が望むことを想像する「普遍的11欲求」、未来の生活行動時間を予測する「Future Time Use」、生成AIを活用して未来の生活者像を具体化する「未来人ジェネレーター」などを使うことで、つくりたい未来像を解像度高く描くことができます。
AI時代だからこそ必要な思考力
「未来コンセプト」を設定する上で、吉田さんは「思考すること」を重視しているそうですね。その意図を教えてください。
今、AIによりアイデアや視点をたくさん出せるようになっています。ただ、数多くの案から良し悪しを判断するのは人間です。未来がどうなっていくのか、どうすればより良い未来になるのか、アイデアをかみ砕き深く思考しなければ、目利きはできません。AIのアイデアを判断する力と、AIにはない思考の積み重ねがなければ、いくらAIが進化してもビジネスの成功には結びつかないと思うんです。
また、自社の価値を高めるには、ビジョンやブランドをしっかり打ち出し、生活者がどれだけその企業や商品・サービスにポジティブな印象を持ってもらえるかが重要です。「この商品・サービスは、あなたにこんな幸せを提供します」という特別な価値を提示し、そこに対価を払ってくれるターゲットに届けることで利益は生まれます。企業側が「これがあるべき未来なんだ。その幸せを提供するんだ」と確信を持てる状態にするためにも、さまざまな観点から考え抜くしかないと思っています。
この書籍の中でも、未来のビジョンに確信を持ち、社内で共有することを重視していましたね。
そうなんです。ビジネスや商品・サービスは、一人ではつくれません。強い意志と明確なビジョンを持つ人が旗を立て、共感する人を巻き込んでこそ、未来づくりの一歩が始まります。そのためにも、徹底的に考え抜いて確信を持つことが大事です。
「未来コンセプト」を設定するとどんな未来を実現できるのか、成功事例を教えてください。
未来事業創研でご支援した事例ではありませんが、岐阜県高山市の国際観光都市化(※)は素晴らしい事例だと思います。高山市は1980年代からインバウンド対策に取り組み、2024年には人口の9倍以上もの外国人観光客が同市に宿泊しました。この事例の最も素晴らしい点は、外国人観光客に合わせて新しいコンテンツをつくらなかったことです。住民はこれまで通りの暮らしを続け、この地域らしさを維持し、それをそのまま観光客に見せる。「地域のリアルをコンテンツにする」という「未来コンセプト」が秀逸でした。
高山市のように振り切った「未来コンセプト」を設定するのは難しいかもしれませんが、すでに強みがある企業は、それを新しい価値に変えて世の中に提供すれば、社会や生活者が求めるものになるかもしれません。
※人口のおよそ6倍、55万人ものインバウンド客が訪れるようになった岐阜県高山市の事例(一般財団法人 自治体国際化協会/2019年)

企業の体力があるうちに「未来」起点で次の一手を
少子高齢化やエネルギー問題など、日本の未来にはさまざまな課題があります。ですが、未来事業創研が提唱する「未来コンセプト」では、あるべき未来、ありたき未来を考えるのでワクワク感がありますよね。
プログラムを実施した企業の方からも、そう言っていただくことが多いです。マクロな視点ではネガティブな未来が待ち受けているかもしれませんが、こうした未来にも幸せは必ずあります。確かに少子高齢化は進んでいきますが、高齢者が多い国が不幸かと言ったらそうではありませんよね。ただ悲観的になるのではなく、どういう視点を持てばどこにどんな幸せをつくれるのかを考えなければ、新しい価値は生まれません。そうやって未来をポジティブに考えるのは確かにワクワクすることです。ただ、実際に新しい価値を創造するにあたっては、苦しいこともたくさんあると思います。こうした局面でも、未来事業創研が伴走いたします。
最後にあらためて、『未来思考コンセプト―ポストSDGsのビジョンを描く』のおすすめポイントを教えてください。この書籍は、どんな企業に効くと思いますか?
まず、「2030年以降に向けてそろそろ新しいことを始めなければ」と考えている企業。加えて、日本をマーケットにしている企業や、バリューチェーンに不安を抱える企業にも効果的だと思います。例えば自動車業界では、エンジンからEV(モーター)へのシフトが一気に進みましたよね。業界の構造が急変する可能性など、現状のバリューチェーンに不安がある企業は、体力があるうちに次の手を打っておくべきです。また、「事業のオプションを考えたい」「ここ数年、ヒット商品が出ない」という企業は、未来をビジネスツールにするとやるべきことが見えてくるのではないでしょうか。ぜひこの書籍を読んで、「未来コンセプト」の策定にトライしていただけたらと思います。
⇒未来事業創研の書籍『未来思考コンセプト―ポストSDGsのビジョンを描く』のご紹介ページはこちら