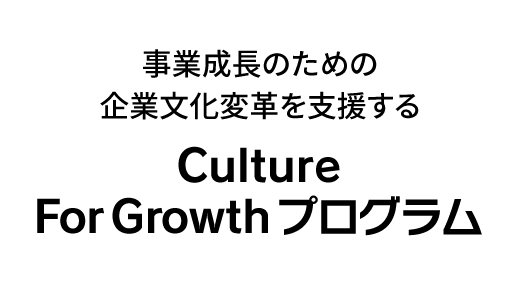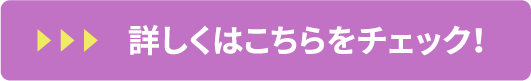企業にとって「周年」は、これまでの歩みを振り返るだけでなく、これからの未来を描く出発点です。このせっかくの機会を、記念式典やキャンペーンなど“お祝い”で終わらせてしまってはもったいない。ということで、周年を「自社の文化を“動かす”契機」として活かし、組織やブランドを再定義する企業も増えています。
本記事では、「周年とは何か」を整理し、成果を上げた企業の実例と、そこから見える成功の共通点を紹介します。最後に、周年を“企業文化変革の起点”にするための実践ステップを解説します。
PROFILE
INDEX
周年とは? その意味と正しい使い方
周年とは“満〇年”を意味する節目
「周年」とは、ある出来事や創業・設立から満〇年を迎える節目を指します。例えば「創立10周年」は、創業から10年が経過した翌日から11年目を迎える前日までの1年間を意味し、「10年目」とは異なります。企業や団体では、この節目を機に式典やキャンペーンを行うことが一般的で、周年イヤーと称して1年かけて記念事業や記念行事を行うケースも多くあります。
過去と未来をつなぐ「新たな挑戦への節目」
本来、周年は“続けてきた証”と“これからも続ける意思”を示すものです。
過去の歩みを振り返ると同時に、未来への姿勢を社会に発信する機会でもあります。
周年を「式典やロゴ制作」といった表面的な施策だけで終わらせず、企業の成長ストーリーや文化を見つめ直す“未来への飛躍の契機”として捉えることが重要です。
企業における「周年事業」とは?
周年事業は、単なる記念イベントではなく、企業の方向性を再定義し、文化を再起動する重要な経営テーマです。目的や対象によって、主に以下の3つに分類できます。
| 区分 | 目的・ねらい | 主な施策内容 | よくある課題 |
|---|---|---|---|
| 社内向け(インナーブランディング) | ・社員への感謝 ・理念・ミッションの再浸透 ・一体感の醸成 |
・記念式典 ・表彰イベント ・社史・ムービー制作 |
・形式的なイベントで終わる ・理念が“お題目化” ・現場への浸透が弱い |
| 社外向け(ブランディング/マーケティング) | ・ブランド価値の再発信 ・顧客・地域社会への感謝 |
・記念広告 ・周年キャンペーン ・特設サイト・ロゴ制作 |
・短期的な話題作りで終わる ・効果測定が曖昧 ・継続戦略がない |
| 経営戦略的(文化・方向性の再定義) | ・企業文化の見直し ・経営理念の再定義 ・変革・次世代への継承 |
・ビジョン再構築プロジェクト ・ワークショップ ・文化変革支援 |
・理念再定義が形骸化 ・行動や制度への落とし込み不足 ・経営層だけで完結 |
周年事業がうまく機能すると、社員のエンゲージメント向上やブランド価値の再認識、部署を超えた連携など、組織全体の一体感が再構築されます。一方、目的が曖昧なまま進行すると“イベント消費”に終わり、本来の価値である「文化の再起動」につながりません。
次章では、こうした周年事業で多くの企業が直面しがちな「3つのつまずきポイント」を整理します。
多くの企業が陥る“3つの周年事業のつまずきポイント”
周年事業は貴重な機会ですが、以下の3つの壁に直面しがちです。
① 目的が曖昧なまま進行してしまう
● 「せっかくの周年だから何かやろう」でスタートし、目的が共有されないまま進む
● 部署ごとに動きがバラバラで、成果が定義されないまま“やった切り”で終わる
② 一時的な盛り上がりで終わり、継続しない
● 式典や動画など単発イベントに偏り、翌年度以降につながらない
● 「その後どう変わったか」を検証する仕組みがないため、文化として定着しない
③ 内向きに完結し、社会との関係を生かせない
● 社内中心の発信にとどまり、顧客・地域・社会への共創に踏み込めない
● 感謝を伝える“内輪のイベント”に終わり、ブランド価値向上に結びつかない
周年事業は「感謝」「発信」「再定義」など多層的な目的を持つ全社的な取り組みです。
これらの課題を乗り越え、周年を“文化を動かす転換点”として活かす企業が成果を上げています。ここからは、そうした課題を乗り越え、実際に成果を上げた企業の周年事業を具体的に見ていきます。
周年事業が成功した実例
多くの企業が周年事業で課題に直面する一方で、“お祝い”を超えて組織やブランドの成長につなげた企業も少なくありません。
ここでは、成果を上げた周年事業の実例を紹介します。
| 企業名/周年 | 主な取り組み内容 | 成果・効果 | 学び・示唆 |
|---|---|---|---|
| メルカリ(10周年) | 「Next 10 Years」を掲げ、全社員でMVVを再定義。グローバル展開とサステナビリティを明確化。 | 理念理解度が社内サーベイで上昇し、採用・定着にも好影響。 | 成長企業ほど、節目に原点を見直すことが次の成長を支える。 |
| 良品計画(30周年) | 「感じ良い暮らし」再宣言キャンペーンを展開。理念を再定義し、社会との関係性を再構築。 | ブランド理念を社会と共有し、生活者との距離を再確認する機会となった。 | 周年を社会との対話の機会とすると、ブランドへの共感が広がる。 |
| コスモスイニシア(50周年) | 「挑戦を続ける50周年」として社員参加型プロジェクトを展開。 | 社内コミュニケーションが活性化し、新規提案が増加。 | 周年を終点ではなく始まりと捉えると、文化が動き出す。 |
| 旭ダイヤモンド工業(創立80周年) | 若手主導で理念を再確認し、歴史を未来に継承する方針を発信。 | 社員間の一体感が高まり、経営理念への共感が強化。 | 周年を“次代をつなぐ場”とする姿勢が文化の更新を促す。 |
| オタフクソース(創業100周年) | 「感謝と笑顔の100周年」をテーマに、顧客・地域と共創イベントを実施。 | 特設サイトやSNSなど複数チャネルで発信を強化し、共創の輪を拡大。 | 周年を“共に祝う”設計に変えると、社会との関係が深まる。 |
成功企業に共通する3つの特徴
これらの企業に共通するのは、未来を動かす仕組みとして設計している点です。
① 未来志向の設計
過去を振り返るだけでなく、「次の10年」など未来を見据えた方向性を明確化している。
② 共創と参加
社員・顧客・地域など多様なステークホルダーを巻き込み、“共に祝う構造”を形成している。
③ 行動と文化の定着
周年後も行動・制度・コミュニケーションに落とし込み、文化として定着させている。
周年事業の共通点は、周年を「感謝の場」だけでなく「変化を生み出す装置」として活かしている点にあります。社員が未来への共通認識を育み、新たな行動を起こすことで文化が進化する──。
こうした“文化を動かす周年”が増える背景には、文化こそが企業成長のカギという認識の広がりがあります。一方で、その狙いや重点テーマは企業のライフステージによって異なります。
では、それぞれの段階で周年はどんな意味を持つのでしょうか。
企業成長段階ごとに異なる「周年の重点テーマ」──すべてに通じる“文化”という視点
企業のライフステージによって周年事業の意義は異なりますが、
共通するのは「文化を整え、次の成長に向けて組織を動かす」こと。
周年は、企業の規模や年齢にかかわらず、文化を見直す絶好の機会です。
| 企業ステージ | 周年における重点テーマ | 背景・目的 | 「文化変革」との関係 |
|---|---|---|---|
| 黎明期(〜10周年) | 成長モデルの共有と期待感の醸成 | 社員・社会に「これからの成長ストーリー」を提示 | 組織としての価値観や行動基準を形成し、文化の“立ち上げ”を行う段階 |
| 成長期(〜30周年) | 原点・価値観の再確認とファンの拡大 | 社内外の共通理解が求められる | 創業の精神を現代化し、文化の“再結束”を促す |
| 成熟期(〜50周年) | 歴史・文化の記録と社会的価値の再確認 | 部門・人材が多様化し、組織間の連携が課題に | 社内外で文化を共有し、文化の“再統合”を進める |
| 転換期(50周年〜) | ブランド再構築と新ビジョン提示 | 社会や市場の変化に合わせて企業の存在意義を再定義 | 既存文化を刷新し、文化の“変革”を推進する |
周年の捉え方は企業のステージによって異なりますが、
共通する本質は「文化を見直し、次の成長につなげること」です。
価値観を共有し、行動をそろえる――。
いま、多くの企業が周年を“文化変革の機会”として捉え始めています。
企業の文化変革とは
文化変革とは、制度や仕組みを変えることではなく、人の価値観や行動の前提を変えることです。理念を「掲げるもの」から「行動を導く軸」へと進化させ、組織が自律的に動く文化を育む取り組みと言えます。
文化が変わることで、次のような効果が生まれます。
● 変化への対応力(レジリエンス)の向上:事業環境の変化に柔軟に対応でき、望ましい方向に進むことができる。
● ブランドの一貫性強化:業務やステークホルダーに対する姿勢や発信が揃い、企業の信頼が高まる。
● 社員エンゲージメントの向上:理念への共感や矜持が深まり、自律的に動く社員が増える。
周年という節目は、この文化変革を自然に始められる貴重なタイミングです。
過去を振り返りながら、未来を描き、組織を動かす“共通の物語”を再構築する機会なのです。

なぜ今、周年を“文化変革”の機会にすべきなのか
変化のスピードが増す今、企業に求められているのは、変化にしなやかに適応できる文化=レジリエンスです。文化はもはや内面ではなく、変化を生み出す経営資産。だからこそ、多くの企業が「文化変革」に注目しています。周年という節目は、その文化を見つめ直し、未来への挑戦を始める絶好の機会です。
周年が文化変革に適している3つの理由
1. 全社を巻き込む共通言語がある
部署や階層を超えた対話が生まれやすく、理念やビジョンの再確認にも最適
2. 過去と未来を接続できる
これまでの歩みを振り返りながら「次の10年」「次の100年」を語る場となる
3. 文化を“見える化”しやすい
式典・ムービー・メッセージ・ワークショップなど、多様な形で文化を表現できる
周年を“文化変革の装置”として捉えることで、理念の再定義や社員の意識統一を越え、実際の行動変化・価値創出の循環を生み出せます。
周年を文化変革の起点にする3ステップ
周年を「文化を変える装置」として機能させるためには、
現状の可視化→未来像の共創→行動への定着という流れが重要です。
| ステップ | 目的・狙い | 具体アクション | ポイント |
|---|---|---|---|
| STEP 1:現状を見つめ、変えるべき文化を特定する | 残す文化と変える文化を整理し、組織の“現在地”を共有。 | 社員アンケートや対話で価値観を可視化。 | 美化せず、事実を共有する姿勢が信頼を生む。 |
| STEP 2:次の10年を見据えた“ありたき姿”を描く | 理想の姿を共創し、行動の軸を定める。 | ビジョンワークや周年テーマの策定。 | 物語として語ると共感が広がる。 |
| STEP 3:未来像を“行動と仕組み”に落とし込む | 新しい文化を日常に根づかせる。 | 行動指針・制度を更新し、継続的に共有。 | 「動き続ける周年」として定着を仕組みにする。 |
周年は、“文化の再構築を始める年”として位置づけることが、真の成功への第一歩です。
まとめ──周年を“祝う日”から“文化を動かす契機”へ
周年は、企業がこれまでの歩みを振り返り、「次の10年」など未来を見据える貴重な節目です。組織の文化を見つめ直し、未来を描くための機会として活かすことが重要です。
文化は、戦略や仕組みを支える“土台”であり、変化を生み出す原動力です。
周年をきっかけに、その文化を少しずつ動かしていくことで、企業はよりしなやかに、そして持続的に成長していくことができます。その変化を確かなものにするには、文化を再設計し、行動につなげる「仕組み」が欠かせません。
電通の「Culture For Growth」は、自社らしさを生かしながら、変革を推し進めるカルチャーに会社をアップデートするためのプログラム。
周年を節目とし、組織進化の機会へと転換したい・・・でも、どうすれば最良の方策を取ることができるだろう?とお考えの時に、ぜひ参照していただきたいソリューションです。
● 組織文化の課題価値観を可視化し見つめ直す「診断」
● トップから現場までを巻き込む未来に向けた「共創プロセスセッション」
● ムーブメントでは終わらせない行動・制度への「浸透・行動変革定着プロセス」
周年を単なるイベントではなく、「文化を動かす周年」として全社レベルで実現します。
未来を見据え、自社らしい文化を育てる第一歩として、
こうした取り組みを検討してみてはいかがでしょうか。