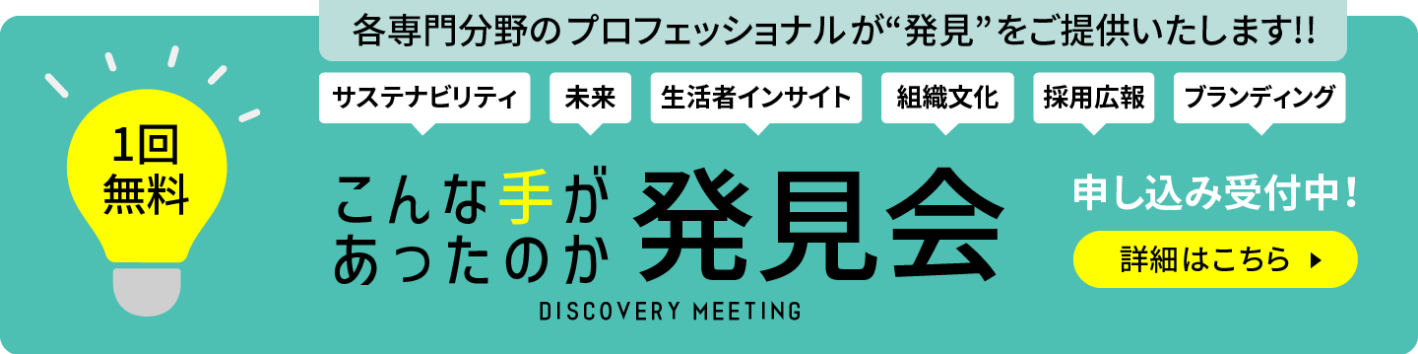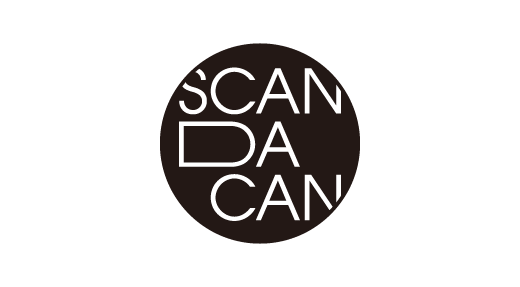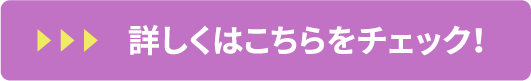販促キャンペーンは、「売上を伸ばすための短期施策」として捉えられがちです。しかし現代では、単に売上を伸ばすことを目的とした施策では、生活者の参加意欲やブランドへの好意といった本来期待される成果を十分に得ることが難しくなっています。
実際、生活者は「得したい」「楽しみたい」といった気持ちでキャンペーンに参加します。一方で、「応募が面倒」「どうせ当たらない」「特典に魅力を感じない」といった理由から、参加をためらうケースも少なくありません。こうした“参加されない”課題を解決するためには、生活者の心理や行動に寄り添ったキャンペーン設計が不可欠です。
本記事では、販促キャンペーンの基本から成功事例までを整理し、生活者起点で考える新しい設計方法を解説します。さらに、電通が提供する購買証明ソリューション「SCAN DA CAN(スキャン ダ カン)」の最新機能を活用した、次世代の販促体験の可能性についてもご紹介します。
PROFILE
INDEX
販促キャンペーンが求められる理由:生活者の動機と企業の目的

生活者の3大動機
● 得したい(割引・特典)
● 試したい(新商品体験)
● 楽しみたい(ゲーム性・イベント)
生活者が販促キャンペーンに参加する動機の多くは「得したい」「試したい」「楽しみたい」という3つの心理に集約されます。割引や特典で得をする喜び、新商品を試すワクワク感、ゲーム性のある施策で楽しむ体験。これらは購買行動を促す大きなきっかけとなり、生活者を「購入者」から「積極的に関わる参加者」へと変えていきます。
企業の3大目的
● 新規顧客の獲得
● リピート購買の促進
● ブランド体験の強化
企業にとって販促キャンペーンは、単なる売上アップだけでなく「新規顧客の獲得」「リピート購買の促進」「ブランド体験の強化」という3つの重要な役割を果たします。特典で初回購買を促し、蓄積型施策でリピートを後押しし、体験型イベントでブランドへの好意を育む。こうした複合的な狙いを同時に満たせる点が、販促キャンペーンの強みです。
生活者の期待と企業の狙いが交わる接点
販促キャンペーンの価値は、生活者の動機と企業の目的が交わる接点にこそあります。生活者は「得したい」「楽しみたい」という期待を持ち、企業は「買ってほしい」「好きになってほしい」と願う。その両者をつなぐ仕組みとしてキャンペーンが機能することで、購買行動は生まれ、長期的な関係構築へと発展します。これが、今も販促キャンペーンが求められる根本理由なのです。
| 生活者の動機 | 企業の目的 |
|---|---|
| 得したい | 新規顧客の獲得 |
| 試したい | リピート購買の促進 |
| 楽しみたい | ブランド体験の強化 |
販促キャンペーンとは?基本の定義と種類
販促キャンペーンの定義と役割
販促キャンペーンとは、自社の商品やサービスを広く知ってもらい、購買や利用へとつなげるマーケティング施策の一つです。短期的に売上を押し上げるだけでなく、体験を通じてブランドへの好意や関心を高める役割も果たします。
代表的な種類
| 種類 | 特徴 | 例 |
|---|---|---|
| クーポン | 割引で購買を後押し | LINEクーポン配布 |
| ノベルティ | 購入特典で満足度UP | 限定グッズプレゼント |
| SNS連動 | 拡散・話題化 | ハッシュタグ投稿 |
| 購買証明 | 購入証明で応募 | レシート・パッケージ撮影 |
手法は多岐にわたりますが、代表的なものとしては、割引クーポンやノベルティのプレゼント、SNSを活用した拡散型キャンペーン、購買証明による応募施策などが挙げられます。いずれも生活者の心理を刺激し、参加のきっかけを作る仕掛けです。
今日の販促キャンペーンの進化 ― デジタル化と新しい参加体験
近年、販促キャンペーンは大きな変化を遂げています。応募の簡便化や不正防止を目的としたデジタル化が進み、パッケージ撮影やアプリ連携といった新しい参加方法が次々と登場しました。これにより、従来「面倒」とされがちだった応募の手間が軽減され、参加体験そのものが価値として捉えられるようになってきています。
このようにして今日の販促キャンペーンは、デジタル化によって生活者の「得したい・試したい・楽しみたい」という動機を従来よりも手軽に満たし、あわせて企業の「新規獲得・リピート促進・ブランド強化」を効率的に実現できるようになってきているのです。
今日のキャンペーンの特徴を理解したところで、次に気になるのは「どんな事例が成功しているのか」ではないでしょうか。ここからは、具体的なアイデアと事例を整理してご紹介します。
成功のヒントが詰まったアイデア&事例集
| カテゴリ | ポイント | 具体事例 | ポイント |
|---|---|---|---|
| SNSを活用した話題化 | 生活者自身が発信することで自然な拡散。ハッシュタグ投稿やシェアが参加条件。 | コカ・コーラ「シェアハピ」 スターバックス「#スタバ新作」 |
拡散性を高めるには「シェアしたくなる理由」を設計することが重要。 |
| 購買証明による信頼性 | レシートやパッケージ撮影を条件に、購入者だけが応募可能。不正防止とデータ活用を両立。 | キリンビバレッジ「午後の紅茶」 ローソン「アサヒ飲料×レシート応募」 |
購買者データを確実に把握でき、CRMやリピーター育成につなげやすい。 |
| ユニーク演出で参加体験を強化 | ARやデザイン投稿など、応募そのものを楽しめる仕掛けでブランド好意を醸成。 | 日清食品「カップヌードル 謎肉祭」 ユニクロ「UTme!」 |
「楽しいから参加したい」という動機を刺激し、SNSでも拡散されやすい。 |
| 応募体験の簡便化 | 手間をなくすUXが参加率を左右。ふたを撮影するだけで応募できる仕組みが継続参加を促進。 | 明治LG21「習慣化キャンペーン」 | 参加ハードルを下げることが応募数拡大のカギ。続けやすさは購買習慣化にもつながる。 |
| 参加理由に基づく設計 | 「得したい」「楽しみたい」といった動機を設計に反映。お得感や遊び心が成功要因に。 | ローソン×PayPay「即時還元」 マクドナルド×ポケモン「ハッピーセット」 |
生活者の参加動機を的確に捉えることで、リピーターやファン形成につながる。 |

事例は多様ですが、どれも「なぜ多くの人がキャンペーンに参加したのか」という問いに明確に応えています。では、自社が成果を上げるには何を押さえるべきか。以下では成功に必要なポイントを整理します。
成功する販促キャンペーンのポイント
成功事例を振り返ると、成果を上げるキャンペーンには共通する要素が見えてきます。
ここでは特に重要な3つのポイントを紹介します。
● 「面倒だからやらない」を「楽しいから参加」に変えるUX
● SNSシェア・口コミを促すデザイン
● 短期成果から長期ファン形成へ
「面倒だからやらない」を「楽しいから参加」に変えるUX
応募の手間が多いと生活者は離脱してしまいます。住所入力や長いアンケートは避け、数秒で完了する仕組みを用意することが重要です。さらに応募時に小さな演出を加えれば、「面倒だからやらない」を「楽しそうだから参加したい」に変えられます。
SNSシェア・口コミを促すデザイン
キャンペーンは参加者の体験をSNSに広げることで効果が増します。そのために、シェアしたくなる結果画面や投稿テンプレートなどを用意することが有効です。「誰かに話したい」と思えるデザインは、自然な口コミを生み、新規参加につながります。
短期成果から長期ファン形成へ
販促キャンペーンは単発の売上増だけでなく、再参加を促す仕組みが重要です。ポイントやスタンプの蓄積、NFTなどで体験を可視化すれば、生活者に継続的な動機を与えられます。短期成果とファン育成の両立がこれからの鍵です。
キャンペーンを成功するためには「参加しやすさ」「拡散性」「継続性」を意識できているかが重要です。以下の3つのチェックリストで、自社の取り組みを点検してみましょう。
<自社の販促キャンペーンを振り返る3つのチェックリスト>
1. 応募体験は“面倒”になっていないか?
2. SNS拡散や口コミを想定した仕掛けがあるか?
3. 単発施策で終わらず、次につながる仕組みがあるか?
応募の煩雑さや体験の物足りなさは、せっかくのキャンペーンを参加につなげられない大きな壁となります。
生活者に選ばれる次世代の販促キャンペーンとは
これからの販促キャンペーンには、単発の売上や参加数だけでなく、生活者との中長期的な関係づくりが求められます。応募体験をシンプルにし、楽しさや共有したくなる仕掛けを取り入れながら、同時に企業のマーケティング資産となるデータを蓄積できる仕組み――それこそが次世代の販促キャンペーンです。こうした新しい方向性を切り拓いている具体例のひとつが、購買証明ソリューション「SCAN DA CAN(スキャン ダ カン)」です。以下では、その特長と最新機能をご紹介します。
新しい販促体験を拓く、「SCAN DA CAN」
「SCAN DA CAN(スキャン ダ カン)」は、マストバイ型の販促キャンペーンに適した、電通の先進的なデジタルサービスです。生活者が商品パッケージをスマートフォンで撮影するだけで販促キャンペーンに参加できるようにし、応募時に感じる面倒な体験を楽しい体験に変え、中長期的な関係づくりにつながる仕組みを提供しています。
デジタル購買証明の機能を持つこのサービスは、従来のレシート応募に比べて応募の手間を大幅に減らして、生活者に参加しやすい体験を提供しています。また、巧みにデザインされたUXが応募時の楽しい体験の提供を可能にしており、参加促進や話題拡散の可能性を高めるように設計されています。企業はIDベースの飲用データを取得できるので、そのデータを継続的なCRMやロイヤルティ施策に活用することで、単発施策で終わらない中長期的な関係につなげていくことかできるようになっています。

新たに加わった4つの進化機能
今年、この「SCAN DA CAN」に、4つの新機能が搭載されました。いずれも、これからの販促キャンペーンを、生活者と企業双方にとっての価値を高める「次世代の販促キャンペーン」にするために拡充された機能です。
● 迅速・低コスト導入を可能にするテンプレート「SCAN DA Light」の活用
● マーケティング解析力を強化する画像解析AI「カロミル」との連携
● 参加の楽しさを拡充するクオリティの高いオリジナルゲーム:「GameBox」との連携
● ロイヤルティ設計に向けたデジタルスタンプ 「NFTスタンプ」の付与
これらの機能は、生活者心理に寄り添う販促キャンペーン設計をさらに後押しします。詳細な事例や活用シナリオについて、無料eBookにて詳しくご紹介しておりますので、ご関心のある方はご覧ください。
まとめ|販促キャンペーンを“売上”から“関係づくり”へ

ここまで見てきたように、販促キャンペーンは短期的な売上だけでなく、中長期的な関係づくりを視野に入れることが欠かせません。最後に、そのための3つの視点を整理します。
● これからの販促キャンペーンに求められる視点
● テクノロジーを活用した効率化と体験価値の両立
● 「SCAN DA CAN」で実現する次世代の販促DX
これからの販促キャンペーンに求められる視点
従来は短期的な売上が中心でしたが、今後は「参加のしやすさ」や「楽しさ」といった体験価値が重要です。売上とともにファンを増やし、持続的な関係を築く視点が成功の鍵となります。
テクノロジーを活用した効率化と体験価値の両立
応募の簡便化やデータ連携、体験演出など、テクノロジーはキャンペーン進化を後押しします。効率化と体験価値を両立させることで、販促は「施策」から「顧客体験デザイン」へと広がります。
「SCAN DA CAN」で実現する次世代の販促DX
「SCAN DA CAN」は、撮影するだけで応募できる簡便性と、不正防止やデータ活用を兼ね備えたソリューションです。テンプレ活用、食事データ連携、ゲーム化、NFTなどで効率化と体験価値を両立し、生活者に選ばれる次世代の販促DXを実現します。
よくある質問(FAQ)
Q1:販促キャンペーンは必ず売上につながるの?
→ キャンペーンの設計の仕方によりますが、多くの場合、短期的な売上増加や新規顧客の獲得につながるケースが多いです。ただし一過性の売上で終わらせず、キャンペーンを通じて得たデータを分析し、次回施策やCRMに活かすことで長期的な効果が出ます。売上だけでなく、ファン基盤をどう築けるかが重要な視点です。
Q2:販促キャンペーンは小規模な予算でも導入できるの?
→ 可能です。SNS投稿やクーポン配布など、低コストで始められる方法も多数あります。さらに、「SCAN DA Light」のようにテンプレートを活用できる仕組みを使えば、費用や工数を抑えつつ購買証明キャンペーンを実現できます。小規模でも「やれることは限られる」ではなく「効率的に成果を出す」発想がポイントです。
Q3:成功と失敗の分かれ目は?
→ 最大の違いは「生活者が参加する理由を設計に反映できているか」です。特典や抽選だけでなく、「やってみたい」「シェアしたい」と思える体験を用意できるかが成功を左右します。また、応募データをその場限りにせず、次のプロモーションや商品開発につなげられる仕組みを持てるかどうかも大きな分岐点です。