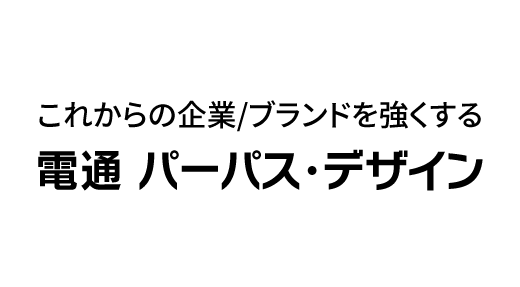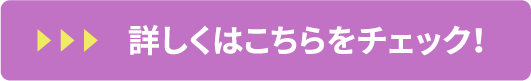INDEX
今、多くの企業や組織が、自らの「パーパス」を策定し掲げていたり、あるいは策定を検討しています。一方で、作ったパーパスが残念ながらうまく社内に受け入れられない・作ろうとしてもうまく進まない、という声もよく聞きます。
私たちは、数多くのパーパス策定のプロセスに寄り添う中で、ほとんどのケースで直面する「3つの壁」があることに気が付きました。
・ なぜパーパスを作るのかがハラオチできない(=準備期の壁)
・ どうすれば思考を深められるのかがわからない(=深考期の壁)
・ この言葉で本当にいいのか?がわからない(=言語化期の壁)
これらの「壁」に共通するのは、「人の気持ち(ヒューマン・ファクター)」に関する問題であることです。人の気持ちに起因することなので、そう簡単には乗り越えられませんし、かといっておざなりにすれば後で苦しむことになります。
私たちは、これらの壁を乗り越えるにあたっての心構えと、適切な「突破の手段」を体系化し、「3つの支援」として提供しています。
このブログでは、パーパス策定の過程での疲弊や迷走を回避し、策定の工程そのものを組織にとって意味あるものにする方法を、電通 ビジネストランスフォーメーション・クリエイティブセンターの福永と宮村がご紹介します。
PROFILE
パーパス策定の3つの壁。その本質は「人の気持ち(ヒューマン・ファクター)」
パーパスの本質とは、関わる一人ひとりが「会社の未来を自分ごと化」し、「主体的に心をひとつにしていく」ことです。
パーパスは「働く人の気持ちに働きかけ、主体性に火をつける」からこそ有用なのであり、もともとパーパスは不確実な「人の気持ち」というものを相手にしているわけです。
だからこそ、パーパス策定には気難しい「人間の心理」とどう向き合うのかという側面がそもそも内包されており、そこをおざなりにするわけにはいかないのです。
では、それらの「壁」とは具体的にどのような課題なのでしょうか。
パーパス策定の壁① なぜパーパスを作るのかがハラオチできない(=準備期の壁)
企業の現場の皆さまは、毎日それぞれにベストを尽くし、忙しく働いていらっしゃいます。そんな方々に、例えば上層部から「パーパスが必要だ」という問題提起があったとしたら、現場の方はどんな気持ちになるでしょうか。ひょっとすると、それまでの自分の働きを否定されているような微妙な印象を与えるかも知れません。
またワークショップに参加するにしても、忙しい時間の合間を縫ってわざわざ参加する心理はネガティブになりがちです。パーパス策定の本質的な目的は「人の心を動かすこと」なのに、これでは初動からうまくいかなくなります。参加者の気持ちが動く巻き込みのプロセスが必要ということです。
パーパス策定の壁② どうすれば思考を深められるのかがわからない(=深考期の壁)
いきなり「会社の未来について考えてみよう」と言われても、どうやって考えればいいのかわからないものです。
会社の情報を棚卸するだけでは「現状の把握」はできても、まだ見ぬ未来への、わくわくするような仮説は立てられません。それは、この手の「未来を考える」という発想法が、日々の仕事の中で必要な思考方法とは異なるからだと考えられます。
思考を深め、その結果として今までにないようなアイデアを生み出すには、クリエイティブで自由な思考を誰にでも可能にするプロセスが必要になります。
パーパス策定の壁③ この言葉で本当にいいのか?がわからない(=言語化期の壁)
パーパスは誰もが日常的に触れ合う「言葉」でできています。逆に言えば、「所詮、言葉でしかない」わけでもあります。
そしてその言葉の力で「一人ひとりの心を動かすこと」が、パーパスに要求される機能ということになります。このとき、言葉が人間の心にどのように作用するのかを意識することが非常に大切です。
言いたいことをただ詰め込んだり、清く正しい言葉を連ねるだけでは、多くの場合、人の心は動かないものです。人の心が動くメカニズムを知り、人の心を動かす言葉の有り様を適切に判断するスキルが必要になります。

パーパス策定は、皆で建設的に向き合う「パーパスドリブン体験」そのもの
パーパスが機能し、一人ひとりの主体性によって組織や個人が駆動されることを「パーパスドリブン」と言います。結婚披露宴でのケーキ入刀が「お二人の初めての共同作業」と言われますが、パーパスに関しては、その策定工程そのものが「初めてのパーパスドリブンな体験」に他なりません。
「我が社のパーパスを策定する」という共通目的に対して、それぞれが使命感を持ち、力をあわせて生み出すという体験です。
その思考と行動の成功体験は、パーパスの出来栄えだけでなく、その後の効果を大きく左右する鍵となります。その意義を最初からわかっていることが非常に重要になります。
準備期にすべきこと=使命感というマインドセットの醸成
まず最初のハードルは、パーパス策定プロジェクトをどんなメンバーで始動するのか、その他の人々はどのように参加できるのかという仕組みを決めることです。
そこで意識すべきは、変えたい、あるいは変えずに大切にしたい社風や文化はなんなのかを見極める視点です。
次に、集められたメンバーの皆さんには「なぜパーパスが必要なのか」「それを考えるのがなぜ自分たちなのか」を、アタマではなくハートで共有します。
それぞれの主体性に火をつけるための重要なトリガーは、「このまま進むと未来はどうなるのか」というリアルな想像とその共有です。この段階で「使命感」の炎を宿すことができるかどうかが最大の鍵です。丁寧に準備しましょう。
深考期にすべきこと=深く考える方法を知り、体感してみる
パーパスを考えるには、いつも考えている以上に深く、様々なテーマを掘り下げて考える必要があります。
非常に頭を使うことになるので、当然、疲れます。毎日の忙しい本業がある中で、そんなパーパス策定に参加するのは大変な負担になりますが、準備期で使命感を醸成できていれば、それを用いて次のステップに前向きに移ることができます。
深考期では「深く考える方法」の存在を知り、その実践を通じて自分が考えていたことの本質やその意外性に気づくことで「そもそも考えることは楽しい」とか、「クリエイティブな発想ができると嬉しい」という実感を得て、積極マインドの好循環を生み出します。
メンバーの皆さんにとって、パーパス策定の時間が楽しみで、有意義になるような時間になっていけば、できあがるパーパスもまた、質の高いものになるはずです。
言語化期にすべきこと=自分の心が動くかどうかを基準にする
先述した通り、パーパスは所詮、言葉に過ぎません。しかし、されど言葉なのです。なぜなら人の思考は基本的に言語でできているのであって、数学と音楽を除けば、人は言葉以外に他者との共通のコミュニケーション手段を持たないからです。そして公民権運動のマーチン・ルーサー・キング牧師の例を見るまでもなく、言葉はときに大勢の人を動かし、歴史さえ動かすほどの力を持っていることもまた事実なのです。
しかし、言葉にすれば伝えたいことが必ず伝わるわけではありません。むしろ「伝える」と「伝わる」は別であることの方が多いものです。受け止めた人がアタマで理解できたとしても、ハートが動かなければ、その言葉はパーパスとしては機能していないということになります。企業のパーパスとなると自分以外の多くの人にも共通に理解されるべきという配慮から、「正しく伝えなければ!」という意識が強くなりすぎてしまいがちです。その結果、「正しいけれど(=誰からも否定はされないけれど)心にも響かない」という交通標語のような言葉に落とし込まれるケースが多々あります。
確かに多くの人の意見の最大公約数は安心感がありますが、パーパスに本当に必要なのは安心感ではなく「心が動き、行動につながる」ための発火装置としての機能です。
正しさや納得よりも(もちろんそれも重要ですが)、「使命感と、アドレナリン」。自分の心が動くか、という指標をいつも見失わないことが重要です。
パーパス策定を成功に導くのは「装備・掘り下げ方・シェルパ」の存在
これまでご紹介した通り、パーパス策定にはヒューマン・ファクター(人の心理)に起因する3つの壁があり、私たちはそこを超えていくための方法論とツールを体系化し、提供しています。どれもが有機的に連携し、皆さまの心に火をつけ、それを維持するサイクルを動かすことを目的にしています。
【装備】 本質を探る思考法「ルーツ・シンキング メソッド」
課題を解決するために最も重要なことは、「そもそも課題がなんなのか」をしっかりと見つけ出すことです。課題の設定がまちがっていれば、どんなに優秀な解決策もまちがったものになってしまい、結果、失敗に終わってしまうからです。
課題を見極めるためには、まず始めに自分たちが日々当たり前のように取り組んでいることを深く深く掘り下げ、その本質はなんなのかを再定義する必要があるのです。そしてその思考過程は「そもそもその商品やサービスは何をしているのか・なぜ必要なのか」を掘り下げ、メッセージのコンセプトをつくりあげる工程と同じ姿をしているのです。
ルーツ・シンキング メソッドは、私たち電通のクリエイターが、広告クリエイティブのフィールドで培った「物事を深く掘り下げ、新しい発想を生み出す」という思考の方法を体系化し、ワークセッションに落とし込んだものです。

「ルーツ」とは、根っこ、つまり根源のことです。「それはなぜだろう?」という問いを繰り返すことで、思考の根源を探究していくということです。また、思考を自由にしてひとつのことからどんどんとアイデアを広げていく様子が、植物が地面に根を張っていく様子に似ていることも語源となっています。
こうして普段は考え及んでいなかった領域まで思考を深め、本質を捉えていくのです。しかし自らに対して「WHY?」を繰り返すことは、想像するほど簡単ではありません。だからこそ、脳の使い方のコツを掴むためのガイドが必要になるのです。広告領域のクリエイターは、コンセプトメイキングの際に「人の気持ち」をベースにしてこの思考を繰り返す訓練を重ねていますから、その方法を共有することが有用というわけです。
「なぜ?」がわかれば人は使命感を持つことができ、主体的に考え、判断し、行動することができるようになります。
「ルーツ・シンキング」はパーパスのような本質的な存在意義を再定義するときには非常に有効な思考・発想法であり、しかもそれをクリエイターの専売特許ではなく、どんな人でも活用できるように組み立てたものです。
【掘り下げ方】 考える力を引き出す「思考のドリル」
長い時間をかけて、ウンウン唸っていると、たっぷり考えたような気持ちになりますね。けれどよくよく思い返してみると、実は「どうしよう?」と悶々としていただけで、頭を働かせて解決方法を生み出そうとはしていなかった、という経験はないでしょうか?
「悩む」と「考える」はちがうのです。
時間をかければ良いアイデアが思い浮かぶわけではなく、短時間ではいい加減なものしか生まれないわけでもありません。大切なのは緩急です。ボーっと無意識に考えるときと、集中して考えるときを行き来することで新しい発想は生まれます。ワークセッションでは普段の無意識ではなく、目的意識を持って短時間に集中します。しっかりと脳を動かして「考える」ことができれば、それほど長い時間をかける必要はありません。
ピッチャーがマウンドで豪速球を投げる前にブルペンでしっかり肩をつくるように、限られた時間の中でルーツ・シンキング メソッドを有効に活用するために、アタマの使い方を理解し、脳をフル回転させてその力を存分に発揮できるように準備をします。
そのために体系化したのが「思考のドリル」です。例えば頭に思いついたことを即座にアウトプットする方法や、自分が考えたことの中に眠っているメッセージを発見する方法など、適切な脳のウォームアップをすることで、驚くほどスムーズに頭を働かせ、自由に発想することができるようになります。
そのような丁寧な準備をすることで、ワークシートの1枚1枚の付箋の質が上がり、情報の単なるまとめや図表へのプロットではなく、創造性に満ちたアウトプットが生み出せるようになります。

【シェルパ(伴走者)】 準備から、策定、浸透までを伴走するパートナー
同じ部署、同じ会社のメンバーだけで話し合っていると、様々な要因から袋小路に陥りがちになります。そんなとき、思考や対話を促してくれる第三者がいることによって、そこにいるメンバーの力が足し算ではなく掛け算になっていくことは、想像に難くないでしょう。
特にパーパス策定のように、多くのステークホルダーが存在し、込み入っていて目的地を見失いやすい課題に関しては、企業や組織のメンバーの中にシェルパ(伴走者)としての第三者が入っていることが非常に有効です。その存在が従来の組織の壁を壊し、心理的なハードルを下げ、新しい発想への柔軟性と寛容さを生み出すからです。
シェルパとは、登山のときに道案内役をしてくれるスペシャリストのこと。地形や天候などという様々な側面から山を熟知し、どんなときも無事に頂を目指すという目標を見失わず、刻々と変わる状況を判断しながら通るべき道を提示してくれる存在です。
パーパス策定におけるシェルパは、「ちゃんと機能するパーパスの策定」という頂(いただき)を目指し、どの道をどのように通っていけばいいかを共に考え、皆さまに最後まで丁寧に伴走します。準備期では関係者との合意形成や人を巻き込むプロジェクト推進を。深考期では、考え方や考えるべき視点・視座、発想を促すヒントなどを横から支えます。言語化期になると、言葉と心の関係性や、ハッとする気づきを与えるコツなどが頼りになるはずです。また、パーパス策定後には、その実践と浸透というフェーズが待っています。
私たち電通は、コミュニケーションを通じて「人の気持ち」と関わってきたプロフェッショナルです。参加者の発想を促し、ポジティブな気持ちを引き出すファシリテーターや、具体的に思考を言語化するクリエイター、プロジェクト全体を正しく前進させるプロデューサーなど、経験豊富なメンバーが支援チームを構築し、ルーツ・シンキングシェルパとして最後まで丁寧に寄り添い、伴走させていただきます。

私たちが丁寧に伴走します。eBookダウンロード、お問合せはお気軽に
改めて、私たちがご提供する「3つの支援」をまとめてみます。
支援 ①装備──独自のメソッド「ルーツ・シンキング メソッド」
→ パーパス策定に欠かせない「自己を振り返り、社会や未来と照らし合わせた上で思考を深く掘り下げ、その本質を抽出する」ためのワークショップのメソッド
支援 ②掘り進め方──「思考のドリル」
→思考を深く掘り下げるために、頭を効率的にフル回転で働かせるための実践的な練習方法
支援 ③シェルパ(伴走者)──伴走する専門チーム
→経験豊富な支援チームメンバー(ルーツ・シンキングシェルパ)が最後まで丁寧に寄り添い、辿るべき道に灯をともす
パーパス策定と浸透のプロジェクトは、それそのものがパーパスドリブンな仕事のあり方や仕事との自分の新しい関係性を体現したものですから、その成功体験こそがパーパスを浸透させていくための最も有効な第一歩になります。
部分でも、全体でも、少しでも気になることがあれば、まずはお気軽にご連絡ください。eBookにも、こちらにない情報を掲載しておりますので、奮ってダウンロードをお願いいたします。