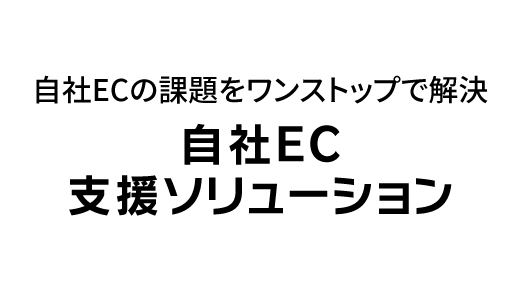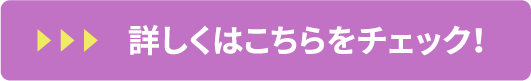近年、デジタル広告の市場の成長とともに、「アドフラウド」いわゆる「不正広告(広告不正)」「広告詐欺」の問題が大きく取り上げられています。NHKをはじめとした各種メディアでも報じられ、消費者庁も注意喚起を促す動きがあるなど、デジタル広告を運用する広告主企業や広告会社に対しても適正な対応が求められています。
そのような中で、
「そもそもアドフラウドって何?」
「どんなリスクがあるの?」
「具体的にどのような対策を講じればいいの?」
と疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか?
この記事では、主に自社で広告運用されている企業の担当者に向けて、アドフラウドの概要、危険性、そしてその対策を、広告主の視点から分かりやすく解説します。
INDEX
PROFILE
アドフラウドとは?
まずはじめに、アドフラウドの概要と種類から解説します。
アドフラウドの概要
アドフラウドとは、デジタル広告における「不正広告」「広告詐欺」を指します。広告を掲載するサイト運営者が、bot(※)などを用いて不正にクリックやアプリインストールを発生させて、不当に広告費を得ようとする行為のことです。
広告主企業にとっては、不正なクリックやアプリインストールによって発生したコンバージョンによって広告費が水増しされてしまうことは勿論、広告の効果を正確に計測できなくなったり、場合によってはブランドイメージを損なったりすることなどが問題視されています。
※bot:インターネット上で事前に設定された処理を実行するプログラム
アドフラウドの種類
アドフラウドには様々な種類があり、多様化しています。ですので、アドフラウド対策を行う上で、どのような種類があるかを把握することは非常に重要です。ここでは代表的なアドフラウドをいくつか紹介したいと思います。
● 隠し広告
WEBサイト上にユーザーには見えない形で広告を表示することで、広告の表示回数を水増しする手法です。
WEBサイトの閲覧自体に影響はありませんが、ユーザーには広告が見えないのに表示回数はカウントされてしまうため、広告主にとっては意味のない広告費用の増大につながってしまいます。また、ユーザーは広告の存在を認識していないので広告をクリックすることはなく、コンバージョンにつなげることも出来ないという、非常に厄介なタイプのアドフラウドです。
● ドメインなりすまし
著名なWEBサイトのドメインを偽り、なりすましたサイトをつくって、広告費を詐取する手法です。
不正なサイトなのでコンバージョンが得られないのは勿論のこと、なりすましのサイトに掲載しているということで、広告主の企業信用力やブランドイメージが毀損される可能性があるため、注意が必要です。
● フローディング
別名「クリックスパム」とも呼ばれており、実際にはクリックされていないのにもかかわらず、架空のクリックを捏造する手法です。
フローディングは、botによって自動的に行われることもあれば、人力で行われることもあります。この被害に遭うと、数値の上でクリック数は増加しますが、その後のコンバージョンは起こらず、成果につながることはありません。クリック数が急激に上昇することが特徴なので、一定期間内で数値が急上昇している場合には、被害に遭っていないか調査することをおすすめします。
● アドインジェクション
WEBサイト上に掲載される広告を無断で差し替え、挿入する手法です。
本来表示されるはずの広告が不正な広告に差し替えられてユーザーに見られなくなってしまうにもかかわらず、広告費用が発生するため、広告主の費用対効果が悪化してしまいます。このタイプのアドフラウドは、ブラウザの拡張機能(アドオン)に不正に仕込まれたプログラムによって発生するケースが多く、ユーザーも意図せず被害に遭っている可能性があります。
● デバイスファーム
大量のデバイスやbotを用いて、不正にアプリのインストールやクリック、広告の表示などを発生させる手法です。
見かけ上の数値は向上しますが、成果には繋がらないため広告主にとっては損をする形になってしまいます。デバイスファームは広告だけでなく、SNSの「いいね」やアプリのレビューなどにも利用される手口です。
アドフラウドの危険性
ここまでアドフラウドの概要と種類について解説してきました。では実際にアドフラウドの被害に遭うとどうなってしまうのでしょうか?ここからはアドフラウドの危険性について解説していきます。
広告費が不正に搾取される
アドフラウドによる最も大きな被害が、不正なクリックや広告表示で水増しされた広告費を支払うことです。不正に計上されていても、多くの広告主はそれが詐欺によるものだと気づくことができないケースが多いのが現状です。
また、本来得られたはずの成果が得られず、費用対効果の低下にもつながります。
ブランド毀損の恐れがある
アドフラウドによって、違法アップロードサイトのような不適切なWEBサイトに広告が掲載された場合、広告を見たユーザーは「こんなサイトに広告を出すなんて」と、広告主に対して不信感を抱いてしまいます。
広告主のブランドイメージの毀損は企業の信用に関わるため、広告主は自分たちの広告がどのようなWEBサイトに掲載されているかをしっかり確認する必要があります。
効果的な広告運用ができなくなる
運用型広告は、広告の成果によって配信内容を逐次設定、改善していくことで、より効果的な広告施策を目指す手法です。
しかし、アドフラウドによって正確な効果測定ができなくなると、配信内容やターゲットや広告予算などについて効果的な広告運用が難しくなり、結果的に顧客獲得の機会を逃すことにつながります。
EC業界においてアドフラウド対策は必須
アドフラウド対策は、EC事業者にとって必須事項です。
EC事業において、デジタル広告は新規顧客やリピート購入を獲得するための手段として非常に有効です。そのため、アドフラウドによって顧客獲得単価が上がってしまったり、正確な効果測定が出来なくなったりすることは事業に大きなダメージを与えます。さらに、アドフラウドによってブランドイメージが毀損してしまうと、新規顧客の獲得に難儀するだけでなく既存顧客が離れてしまう可能性があります。
EC事業者は、広告の出稿先を定期的にチェックしたり、広告配信後のデータを解析するなど、常日頃からのアドフラウド対策を行う必要があります。
アドフラウドを防ぐには

ここまで、アドフラウドの概要や危険性について解説してきました。
では、アドフラウドに対してどのような対策を講じたらよいのでしょうか?ここからは、すぐにできる対策と中長期での対策について触れていきます。
すぐにできる対策①: アドフラウドに対する知識を身に付ける
アドフラウド対策を行う上でまず重要なのは、アドフラウドに対して正しい知識を身に付けることです。正しい知識を身に付けることにより、実際に問題が起こった際に即座に状況を把握し、適切な対処を行うことができます。
最新の知識を身に付けた担当者を配置することが望ましいのですが、自社で難しい場合には、広告会社などの外部の支援会社にアドフラウド対策を依頼することも視野に入れるとよいでしょう。
すぐにできる対策②: 広告配信の結果を分析する
広告の配信結果を分析することで、アドフラウドの原因となっている不正なWEBサイトを発見することができます。CTR(クリック率)やユーザーのアクティブ率、流入元などが異常に偏っている場合はアドフラウドの可能性が高いといえます。もし不正なWEBサイトを発見した場合にはブラックリスト化し、即座に配信停止などの対処を行う必要があります。
また、悪質ではない掲載先をホワイトリストにまとめて、その中でも厳選した掲載先にのみ広告を配信することでブランド毀損の被害を防止することも可能となります。
中長期での対策: アドベリフィケーションツールを導入する
広告配信の分析は、アクセスが少ないサイトであれば、手動で行えるかもしれませんが、大量のアクセスがあるサイトを手動で行うのは大変です。そこで活用したいのが、アドベリフィケーションツールです。
アドベリフィケーションツールとは、配信されている広告が、適切なサイトに掲載されているか、またきちんと見られているかを検証できるツールです。ツールを導入することで、アドフラウド対策の負担が減り、広告戦略立案などのコア業務に集中することが可能となります。
主要ツールベンダーとしては、IAS、Momentum、DoubleVerify Japan、日本オラクル、Spider Labがありますが、それぞれツールの特徴や費用が異なりますので、信頼できる支援会社に相談し、自社の環境に最適なツールを選定してもらうことをおすすめします。
アドフラウド対策なら電通ダイレクトにご相談を
私たち電通ダイレクトは、電通グループのダイレクト領域のリソースを集約した基幹会社です。通販企業や大手メーカーの通販事業のサービスはもちろん、通販商材以外でも多くの商品・サービスでダイレクトマーケティングの支援をご提供し、数多くの実績を有しています。
電通ダイレクトでは、一般社団法人 日本インタラクティブ広告協会(JIAA)の各種ガイドラインに準拠し、無効トラフィックの排除やブランドセーフティの確保を推進しています。
さらに、一般社団法人 デジタル広告品質認証機構(JICDAQ)が定める第三者検証の認証基準に基づき、広告会社(広告購入者)事業領域の「ブランドセーフティ」と「無効トラフィック対策」の2分野において、電通グループの対象事業者として「JICDAQ認証(※)」を取得しており、JICDAQの基準を元に独自のブロックリストを用いた運用も実施しています。
アドベリフィケーションツールの導入をはじめとした、「質の高いデジタル広告運用」を一気通貫でご支援することが可能です。何かご不明点やお困りごとがあれば、お気軽にご相談ください。
→ お問合せはこちら
※JICDAQ認証:JICDAQが定めるデジタル広告の掲載品質確保に関する業務プロセスの認証基準に沿って、広告関連事業者が業務を適切に⾏っているかについて、検証/確認、認証をする制度
関連サイト
● AD Quality 広告品質への取り組み
● JICDAQ(一般社団法人デジタル広告品質認証機構)より ブランドセーフティと無効トラフィック対策における 「JICDAQ認証」を、電通グループの対象事業者として取得